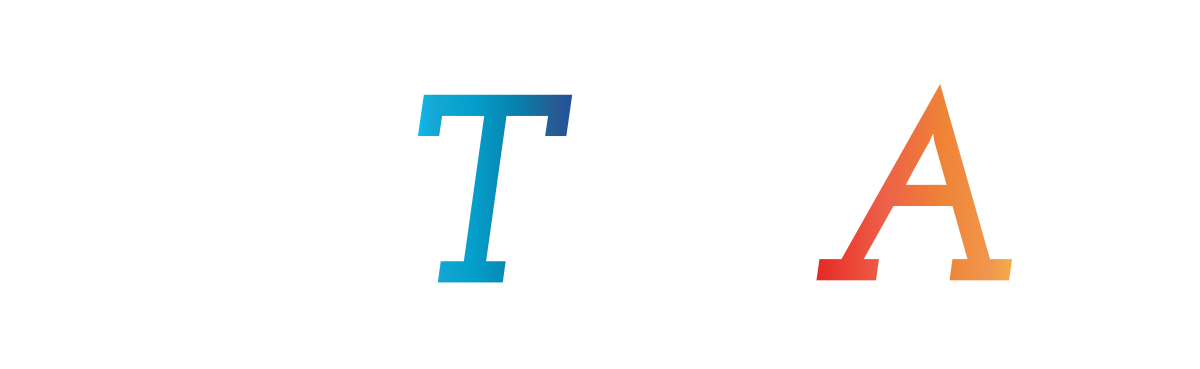発話行為論とは、社会的な行為の意図性や適切性を捉える理論だ。たとえば、食事のテーブルで子どもが親に向けて発する「醤油ー!」は、「醤油をとってほしい」ことを達成するための行為である。その会話で、親は「『醤油をとってください』でしょ」としつけるかもしれない。こうした状況や対人関係に応じた不/適切さが社会的行為には何気なく意識され、時に問われもする。
このような説明をすると、「なにを当たり前のことを」と思うのではないだろうか。かくいうぼくもそう思うのだが、この理論が出てきた経緯を理解すると議論を少し知的に楽しむことができる。そこで、本記事では発話行為論が登場した経緯を中心に解説したい。
オースティンの発話行為論が問いかけたもの
発話行為論を提唱した人物としてジョン・L・オースティン(J. L. Austin)が知られる。オースティンは、命令文や依頼文に見られるように、ある特定の行為を遂行することを「発話行為(speech act)」と呼んだ1。
重要なのが、オースティンは行為を遂行する「行為遂行文(performative)」と、事実を述べる「事実確認文(constative)」に区別した点である。この区別により、従来、言明(statement)が意味する真偽命題や循環論に陥る解釈論に対し、行為として為され、他者・世界に影響を及ぼすことばの力を捉える枠組みが提示された。哲学の中心的な問いのひとつである、「我々はどのように世界を『意味ある』ものとして解釈するか」という問いに答えようとしたのが発話行為論であった2。
この問いに取り組んだのが、1940年代から70年代にかけてイギリス、オックスフォードで中心に活動したオースティンをはじめとした日常言語学派の研究者らであった。ただ、オースティンであれ、その弟子であるジョン・サールであれ、発話行為に関する理論には後に述べるように、彼らの言語イデオロギーが色濃く反映されている。大雑把に言えば、彼らの西洋的な自己意識や責任観が発話行為論を中心とした言語観に表れており、普遍的な理論とはどうしても言い難い。順に解説しよう。
発話行為論──発話行為、発話内行為、発話媒介行為
発話行為論は、発話者が聞き手に行為を遂行する、つまり「力」を行使することに着目する理論である。この理論の登場により、発話行為の達成に向けた適切な社会的条件として話者の意図、誠実さ、権威の有無に注目することへとつながった。
オースティンはそれを適切性条件と呼び、<約束>、<依頼>、<質問>、<警告>、<提案>、<勧誘>などが適切に遂行される条件を探った。この条件を探る上で提示されたのが、発話行為、発話内行為、発話媒介行為である。行為を遂行する発話行為に対し、その指示的な含意を意味するのが発話内行為、その遂行的な行為によって達成されるものが発話媒介行為である。
たとえば、大学にて講師が教室に入った際、「この部屋、暑いですね」と述べる発話行為は、学生に「窓を開けてください」という<要求>・<依頼>を意味する発話内行為となりえる。そして、実際に教室が涼しくなればその行為が現実に達成・影響を及ぼした力が発話媒介行為と捉えられる。つまり、この一連の遂行的な解釈・行為の達成を中心に、社会文化的な適切性条件を探るのが発話行為論である。
発話行為論に対する言語人類学からの批判
では、発話行為論は言語人類学からどのように批判されたのか。ここでは、言語人類学者のデュランティ(2015)“The Anthropology of Intentions: Language in a World of Others”(『意図の人類学』)にてサールの発話行為論に向けられた批判内容を紹介したい。サールは、発話内行為(<約束>、<依頼>など)に焦点を当てて自身の議論を展開した。
サールは発話内行為を次の5つに分けることを提案した。サールによると、②の指図や③の約束は「世界をことばに合致させる(world-to-words direction fit)」もので、対して①の陳述は「ことばを世界に合致させる(words-to-world direction of fit)」方向性をもつ。
- 陳述型
- 指図型
- 約束型
- 表出型
- 宣言型
つまり、サールの理論は<陳述>や<約束>といった発話内行為がいかに世界と一致するかの適切性条件を探るものだった。ここでは③の<約束>として、友達が「明日お昼ごはんを奢るね」と語った例を考えてみよう。もしこの発話をしたら、翌日に友達と昼ごはんを食べ、ランチ代を支払うという義務を発話者が負うことになる。
この捉え方のみでは、話し手が約束をするという意図(intention)と誠実性(sincerity)が「世界をことばに合致させる」条件を構成するものとして本質化される。西洋的な言語イデオロギーとして槍玉に挙がるのがこの意図性で、発話者の意図を中心に発話行為が解釈されてしまう。だが、同じ<約束>でも意図を中心に解釈することができない例が言語人類学者から挙げられている。
たとえば、学会の講演などで“I promise not to bore you with my talk”と遂行動詞であるpromiseを使用する例を日本語に訳せば「私の話で皆さんを退屈させないように努めます」という話し手の<約束>という発話行為ではなく、<願望的(operative)>な意味が表せる3。
サールの発話行為論は、本質化された発話内行為の適切性条件を考慮に入れるだけでなく、裏返しの話し手中心主義の発想が基盤になっており、聞き手や発話行為を取り巻く文脈が考慮に入れられていない4。そのため、サールが挙げた事例は方法論的にもサール自身の内省や直感によって作られたステレオタイプが投影されている。
オースティンからサールといった英米の研究者たちが生きる歴史・社会文化的な言語イデオロギーである話者の意図性や自律的自己には、次のような前提がある。話し手やその所属する社会集団(ここでは大雑把に欧米)で共有される責任の所在や義務の感覚といった集団にコミットするという、規範的な心理状態がかれらの発話行為論に投影されているのだ。
ことばの普遍性と相対性を考える
重要なのは、西洋文化圏の個人的自己観と責任観といった言語文化イデオロギーが発話行為論という「普遍的」とされる哲学に投影されている点である。普遍性を標榜する理論と言えど、それが論じられた文化圏で重視される暗黙理の言語文化イデオロギーがある。
- ジョン・L・オースティン『言語と行為──いかにして言葉でものごとを行うか』(講談社、2019年 [1962年]) ↩︎
- 井出里咲子ほか『言語人類学への招待──ディスコースから文化を読む』(ひつじ書房、2019年、106-115頁)で発話行為論についての概説と、言語人類学からの批判的論点が掲載されている。 ↩︎
- Duranti, A. “The Anthropology of Intentions: Language in a World of Others”(Cambridge University Press、2015年、14頁) ↩︎
- 井出里咲子ほか(2019: 109)『言語人類学への招待──ディスコースから文化を読む』ひつじ書房 ↩︎