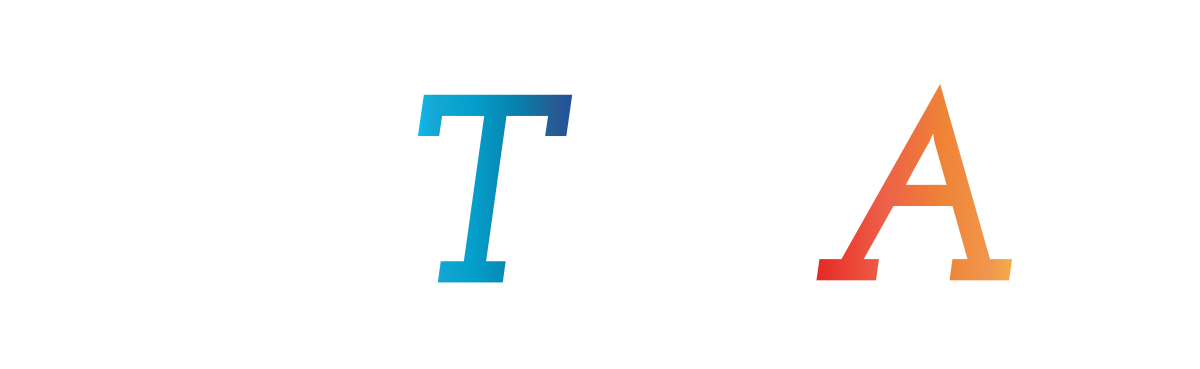社会と文化をどのように峻別するのかという問題は意外にややこしい。従来、社会を方法論的集団主義的に探求してきたのが社会学で、文化をフィールドワークに基づいて多元的に探求してきたのが人類学だ。あくまでざっくりした捉え方ではあるが。
この記事では、基礎概念こそが定義するのに極めて難しいという前提で雑記的に社会と文化についての捉え方について、現時点で考えていることをつらつらと書く。
社会は関係性、文化は精神性
ざっくりまとめると「社会は関係性」「文化は精神性」を根本的に捉えているのではないかと考えてきたが、今考えると「文化は領域性」とも捉えられる。
文化を捉えるにあたって例に出されるのが氷山モデルだ。表層的に海面から現れているものが氷山だと認識できるが、氷山は海底では別の氷山ともつながっているという考え方である。文化を表層と深層の二つの軸で捉える視点であり、そこには精神性とも領域性とも言えるものが確かに表せる。
ただこれまで、ぼくはあまり文化を領域性のあるものだと言いたくなかった。というのも、文化は確かに領域的なもので、一定程度は何かしらがある領域内で共有されていると捉えないと「文化」なるものは見えてこないが、そうすると文化的拘束性と言われるように、文化は人々の思考や行為によって変容していくものだという視点を持ち得にくいと考えてきたからだ。
高橋利枝(2015)『デジタルウィズダムの時代へ』で、「コミュニケーションの複雑性モデル」として「個人・社会・文化」の位相がそれぞれの位相内外でダイナミックな相互作用を及ぼしあって展開されていることがモデル化されている。このモデルをはじめて見たときに感じたのは、このデジタルメディア時代とも言えるような昨今の状況に対して、文化の創発性をよく捉えていると感じたことが大きかった。
このモデルを念頭に入れると、文化概念を領域的なものに閉じ込める志向性だけでなく、領域的な連続性と同時に異なるものへの展開可能性をも視野に入れることができるというわけだ。著者がオーディエンス論を引き合いに議論を立てていることとも関連してこの考え方やモデルが生まれてきているとも言えるだろう。
文化の累積性と連続性
自分自身がデジタルネイティブもとい、デジタルウィズダム的な志向性を持って生活を送ってきたこともあり、文化を領域性だけで語ることはある種の文化決定論だと感じてきた側面もある。ゆえに、文化を「精神性」とすることでなにかしらの行為や慣習をはじめとした「価値(規範)」が伴うものとして捉える傾向にあった。
最近、『メディア・社会・世界 デジタルメディアと社会理論』を読んでいる。その中で、ラトゥールのアクターネットワーク理論に対して批判的な記述をした上で、興味深いまとめがあったので以下に引用する。
ラトゥールは行為の累積的で沈殿化された文脈に関する視点を持っていない。同様に、ジョン・アーリが「移動」の社会学と呼ぶものは、日常的な社会的生活がどのように労働、家族、移民、インフラシステムと結びついたさまざまな「移動」を組み込んでいるのかを捉えているが、これらの移動を結びつける準拠点を無視している。これらの移動が維持されるのは、家、職場、市民が対話を行う場所、資源やルーティンが蓄積される場所にほかならない。
社会的スケールに関するより洗練化された理解とは、フランスの社会理論家ダニーロ・マルトゥッセリが「社会的生活の存在論的性質」と呼ぶものを断念することを意味しない。「社会的生活の存在論的性質」とは、他者との協働や競争において生きられた人間の生から生じる行為に関する「制約」や「強制」の空間的に特有の蓄積である。
『メディア・社会・世界 デジタルメディアと社会理論』40頁
つまり、社会は構造であれ意識であれ関係性を軸に捉える傾向にあるが、文化を考える際には「累積的で沈殿化された文脈に関する視点」が必要であることが主張されている。
今現在、この書籍もラトゥールのアクターネットワーク理論も勉強中なので一概に結論めいたことを言えるわけではないが、まさにこの累積性という視点があることで伝統や慣習といったものに現れる儀礼性が捉えられるという風に解釈がつながった。
言語人類学における指標性・類像性・象徴性の捉え方
パースの記号論を引き合いに出した「指標性・類像性・象徴性」の概念は基礎的概念として言語人類学においてよく援用される。象徴性は概念によく見られるように恣意的・慣習的に説明できるもので、一方で類像性と指標性は慣習的「ではない」ものを理由に説明できるものだ。類像性におけるその理由は類似性・同一性、指標性は連続性・隣接性となる。
象徴性が恣意的・慣習的というのは少しわかりにくいかもしれない。たとえば、「文化」を今まさに僕がこの記事の中で書きながらある特定の意味を浮き彫り立たせているが、それは類像性・指標性を持って書き記しているからこそ別の意味が浮き彫りだっているわけで、逆に言えばわざわざそうしないとこれまで捉えられてきた文化という概念の恣意的・慣習的なものを崩せない。今は文化を主な対象にして論じているからわかりにくいかもしれないが、基本的に文法や語彙といったものもあえて説明しなくても通じることを考えれば、それは慣習的・恣意的だとも言えるわけだ。
現代の言語人類学では大なり小なり、このような捉え方が基本にありつつ、ことばのやり取りの中でどのように言語(文法、語彙 etc.)や人間(社会、文化 etc.)が展開されているのかを探求する学問だといっていい。指標性・類像性・象徴性の観点から捉えると、文化における創発性と累積性も射程に入れることができるのだという納得感が最近湧いてた。それともう一つ重要なのが儀礼性。ヤコブソンの6機能モデルというコミュニケーションモデルで特に重要なのが詩的機能だが、詩的機能とは「メッセージそのもの」が強調される機能を指す。たとえば、オバマ元大統領が「Yes, We Can」と何度も連呼しているのは類像性を用いた詩的機能が前景化していると捉えられる。類像性・詩的機能を用いたコミュニケーションが重なることで、あるやり取りには儀礼性が宿っていく。「あいさつ」というジャンルもその典型だと言える。
つまり、言語人類学的に文化概念は指標性と類像性が積み重なって象徴性、言い換えれば精神性を生み出していくと捉えることができる。そして、それがある集団や領域の中で用いられることで領域性もあるとも言える。
おわりに
これまで文化をどう捉えるかについて、ときに頭を悩ましてきたことが個人的にスッキリしてきたこともあり、雑記的にまとめた。冒頭でも書いたように、学問名を関する基礎的な概念ほど、意外に定義するのが難しい。その定義の如何によって、そこから導出される方法論や分析、考え方も変わっていく。なので、注意しなければならないし、それらを見直すためにはときに「学問」を越えて、理論を見直していくのが有効ではないかと思う。
たまに理論を軽視して「分析あってこそだ」という意見も聞くし、分野における志向性を鑑みればそれも分かるのだけど、やはりそこは一歩ひいて考えねば見えないこともある。個々の問いや追求に敬意を払いつつ、しっかり見直していきたい。