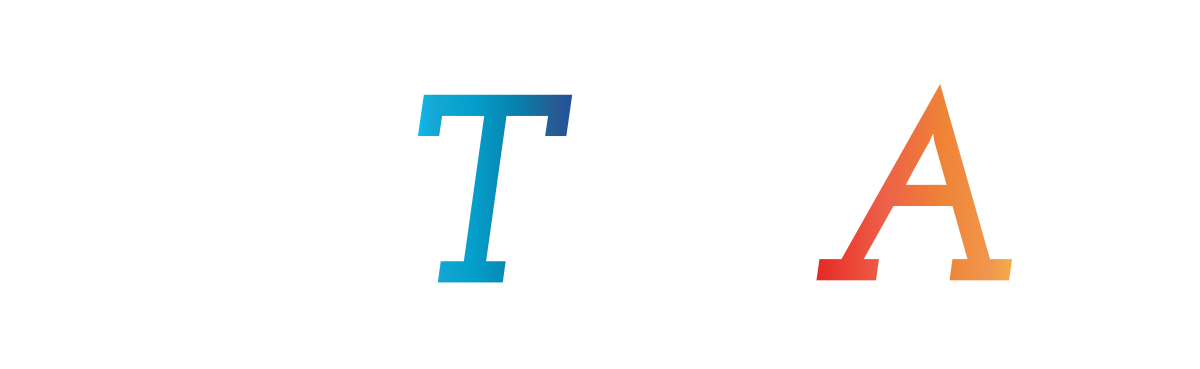「哲学とはなにか」を押さえる上で、「哲学」とこれまでさまざまな哲学者たちによって語られてきた精神史としての「哲学学」を区別する考え方がある。簡単に紹介しよう。
哲学―個々人から全体、普遍への問い
上記の記事では、哲学とは「疑う」ことであるとしたが、さらに言えば単なる「個々人」からの問いかけに終わるのではなく、それを「全体(すべて)」に当てはまるような「普遍的」な応えへと徹底的に追求することにある。つまり、単なる個別のものに終始してしまうのではなく、<全体志向>の学問なのだ。
生きることとはなにか、生きることに意味はあるのか?
たとえば、「生きるとはどういうことなのか」という問いを持ったとしよう。単純に考えれば、「わたしが生まれて、食って、寝て、いつか死ぬ」という話で終わる。けれど、「生とはなにか」という問いかけは、そもそも「わたしとは何か」という問いにもつながる。どういうことかというと、最初に「わたしが生まれる」という部分から、すでに「わたしじゃない誰か」、つまり「両親」が存在する。
それを遡っていくと、「両親にも両親はいる」し、「両親たちにも知人友人」がいるし、そうじゃない「他者」がいるとどんどんどんと連鎖していってしまう。キリがないので問いを「ひとはなぜ生きるのか」と変えたとしよう。問題になるのは、おそらく「生きる意味」だろう。「生まれたときから両親に愛されているとは感じない、なぜそんな状況で生きなければならないのか」。そんな思いがこみ上げた問いかけに対して、「それでも生きることは大切だ。死んでしまっては誰かが悲しむし、迷惑をかけることもある。」と返されたとしても、「なぜ”わたし”が生きる、死ぬということを他人の”悲しむ”とか”迷惑”をかけるとかありきたりな道徳感で判断されなければならないのだろう」と問いかけが生まれるかもしれない。
かつて、戦時中において「特攻」をした兵士たちがいたように、誰かの命令によって、誰かとの関係において「生と死」の意味付けをすることができるかもしれないが、そこで素朴に「なぜ戦争をするのか。なぜ国や街を守る必要があるのか」と、その戦争や争いを行っている意味そのものをさらに問いかけることができる。つまり、自分の命も社会集団の存続の意味は、さらになにか外部にあるものとして求められなければならない、と問いかけていくことができるのである1。
このように、思考をめぐらしていくことで、個々人の「問いかけ」から徐々に全体への「問いかけ」へと向かっていくことが「哲学する」ということの一例だ。
哲学学──哲学史、精神史
一方、哲学学とはこれまで歴史に名を残してきた哲学者たちの考えや知識を学ぶことである。古代ギリシャ時代の生きたソクラテスは「無知の知」と言ったことやその考えに至るまでの経緯、プラトンは「◯◯とは何か」に当てはまるイデアという概念を発案してソクラテスの考えを発展的に引き継いでいった。一方、中世ヨーロッパにおいて、デカルトは善悪や生死とはなにかというおよそ知り得ぬことをどうして知ることができるのか、「そもそもわたしとはなにか」という問いに変化させた。
このように、哲学者同士やそれぞれが生きた時代に影響を受けつつも、「問いと答え」を貯めてきたものを「哲学学」としている。哲学の歴史であるから「哲学史」や「精神史」と呼ばれている2。
問いを学び、問いをつくる営みとしての哲学
哲学と一重にいっても、「哲学する」ことを指しているのか、「哲学学」のことを指しているのかによって、その意味は大きく異なる。私見では、「哲学する」ことがとても重要だと考えている。確かに、古代ギリシャ時代にまで遡っても歴史に名を残した哲学者たちが問いかけたことは、言うなれば「超一級品」で、大多数の人が考える「問いと答え」を凌駕する思考ばかりだ。その歴史に経緯を払って学ぶことはとても大切なことだと思う。
一方で、本来、哲学の核にあるものは「個々人の切実な問いかけ」だと思う。つまり、このわたしにとってどうしても気がかりになること、それを徹底的に考えることこそが哲学の入り口なのである。だから、どんなに過去の哲学者が立派な問いと答えを導き出していたとしても、考えざるをえない問いがあるなら、それを大切にすべきだ。切実な問いをみすみす別の誰かにゆだねてしまってはいけない。
つまり、哲学学で言われていることも「本当にそうなのだろうか」と考えることから、哲学がはじまる。先人たちから問いを学びつつも、問いをつくることこそが哲学するということなのではないか。哲学学で語られてきたことは確かにすばらしい。だが、哲学者たちも歴史の中の一定の時代を生きていた人々なのであり、また一定の地域の中で思考をめぐらしてきた。ということは、どうしても「その時代」「その地域」における影響を受けてしまうのである。であるからこそ、今ここのわたしたちの視点から「問いを学び、問いをつくり、問いを解く」ことには、また新しい意味が生まれる。