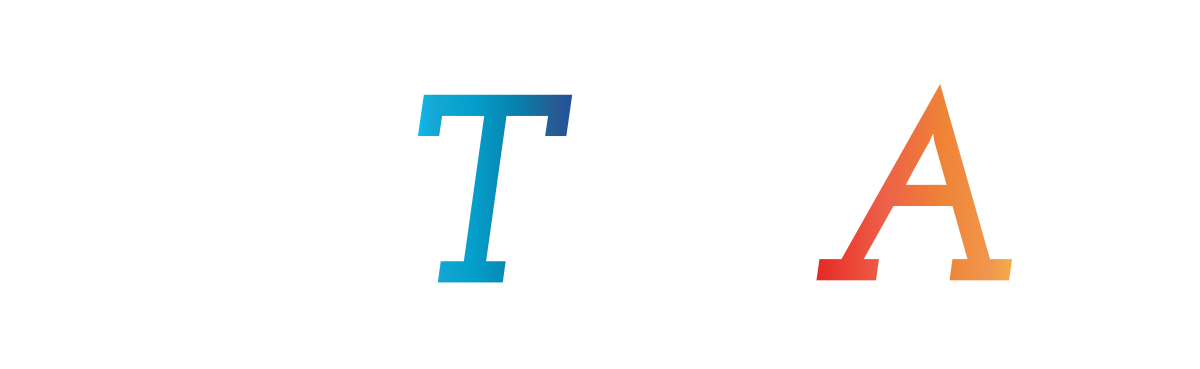最終的にはそれぞれの問いに応じて「哲学する」ことが大事だが、当然、哲学学としてどのような「問いと答え」が積み重ねてきたかを知ることもとても大切だ。哲学の研究をするとなると、普通は一人、もしくは少数の哲学者を選んで文献の調査や論理の追求を行う。哲学を直接の専門分野としなくても、多くの学問分野の根底には「哲学的な問いと答え」として論じられてきたことが存在している1。
また、研究をしない一般の人にとっても、「今ここ」という現代に生きる「この世界」「この時代」を捉えるためにも哲学を知る、知るだけでなく、過去の哲学的な問いを引き継いで考えることはとても価値のあることだと思う。今回の記事では、20世紀までの哲学で、何が論じられてきたのか、哲学を勉強する上で役立つ思考図式と合わせて解説する2。
西洋哲学の基本的な思考図式
まずは以下の哲学的問いの変遷を見てほしい。①~④の思考図式を起点にさまざまな論が展開・転回されていく。必ずしも、このように分かりやすく、哲学的問題が乗り越えられているわけではないが、おおよその流れをはじめに押さえるに当たってとても便利な図式だ。難解な哲学を理解するための補助輪として活用できるだろう。
- 「~とは何か」(プラトン)
- 「わたしとは誰か、なにを知りうるのか」(デカルト)
- 問い①×②(カント)
- 「なぜそれを問うのか」(ニーチェ)
哲学思考図式Ⅰ:「~とは何か」(プラトン)
哲学的な問いの第一段階はソクラテスやプラトンをはじめとした「~とは何か」という問いを持つに至ったことだ。ソクラテスは、目上の者にも臆することなく問答を繰り返すことによって「定義や本質とは何かを問うことで日常から半歩外へと飛び出す」、哲学の基本的な姿勢を確立した哲学者だ。一方、ソクラテスの弟子であるプラトンは、ソクラテスが問いかけた「善とはなにか」というものに「イデア」という名前をつけた。つまり、曖昧模糊とした概念のことを「イデア(見られた真の姿)」とし、「現実とイデア」という二つの思考枠組みを作り上げたのである。
「現実とイデア」という相異なる二つの概念という二項対立によって世界全体を捉えようとする思考図式をプラトン主義という。このように、哲学では日常で当たり前と思うことをそもそも疑うこと、全体志向をすること、さらに首尾一貫した体系的な考え方を探求していく。
哲学思考図式Ⅱ:「わたしとは誰か、なにを知りうるのか」(デカルト)
第二段階になると、そもそも「~とは何か」と問うている「わたしとは誰か」という問いに展開されていく。第二段階の問いを切り開いたのは「我思う故に我あり」という有名なことばを残しているデカルトであり、古代ギリシャ時代から中世ヨーロッパという、実に長い時間を経て新たな問いに展開されたのである。
第二段階の問いは主観・客観の問いだとも言える。主観とは、「自分から見たまなざし」のことであり、言うなれば目から見えている世界を捉える考え方のことをいう。一方、客観とは、「自分を別の角度から見たまなざし」のことであり、言うなれば神のように上から見ている世界を捉える考え方のことをいう。このような捉え方が、西洋の基本的思考の枠組みで、キリスト教的な世界観である「私と神」が「主観と客観」とそれぞれ対応している。
哲学思考図式Ⅲ:問い①×②(カント)
第三段階の展開をもたらしたのは、近代を生きたカントであった。カントはデカルトを代表とする「大陸合理論」とロックを代表とする「経験主義」における対立を調停した哲学者とされている。カントは『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』の三大批判書を著すなど、哲学思考図式Ⅱである認識論を乗り越えようとした。貫(2004)によると、「諸物や宇宙の存在を前提とした上で、それをどうやって認識するかをさぐるのではなく、およそ諸物や宇宙などの存在者が存在者として成立するための条件をさぐる哲学」であり、これを超越論的哲学という。
つまり、カントは超越論的哲学を展開することで、経験する・される対象であるものの存在と「わたし」をはじめとした主体の成立の条件を解明しようとし、哲学思考図式Ⅰにおける万物の存在する根拠となるイデアを、主観の認識メカニズムとなる哲学思考図式Ⅱの考えに落とし込んだ、包括的な説明を論理的に展開したのである。もっと簡単に言うと、主体そのものと認識対象の成立する条件を説得的に説明したのがカントの哲学なのである。
哲学思考図式Ⅳ:「なぜそれを問うのか」(ニーチェ)
最後に登場するのがニーチェで、彼はこれまでの哲学的思考図式ⅠとⅡを根本的に転覆させてしまった。言うなれば、ニーチェの哲学は反哲学なのである。ニーチェ哲学のキーワードは「ニヒリズム」「永劫回帰」「力への意志」という三つに整理できる。
まず、ルサンチマンは「真善美」といった価値は「弱者が強者に対する”妬み”」が起源となって生まれた価値だと断じた。つまり、価値は世界の外部に根拠を持つのではなく、世界の内部における心理的、社会的な力関係から生まれたものなのだという。ニーチェの哲学は明確に「キリスト教」に対し批判的であったことが特徴で、「神は死んだ」と宣言している。
永劫回帰とは、「すべては永遠の繰り返しで、なにも変化しない」ことを指している。ニヒリズムによって真善美といった価値は欺瞞であることが明らかになった。そのため、善悪の価値尺度がないのだから、「より良い」とか「より悪い」ということは判断することなどできないというのである。
永劫回帰を提示することで、ニーチェは私たちに問いかける。「お前の生をもう一度、いや無限回生きることを欲するか」と。その問いかけに「わかった、もう一度!」と心の底から応える瞬間、それが永劫回帰を乗り越えた存在である超人への道だとするのだ。つまり、捨て身の肯定をすることによって人間を超えた存在のことを超人というのである。超人にとっては「すべてはさまざまな力が相克(そうこく)しあう”力への意志”」となる。複数の力が互いに拮抗している状態、力への意志がすべてだとニーチェは言い、「意志は意志することはできない」ということをわれわれに叩きつける。
こうしたニーチェの反哲学は、プラトンのイデアや神といったものを無効にし、「わたし」としての主体も否定することにとって哲学的思考図式ⅠもⅡも、そしてⅠとⅡを組み合わせたⅢも無効にしてしまった。要するに、何か超越的な存在を否定し、すべての存在を力のせめぎあいによって生まれる流動性を肯定していく姿勢は、現代哲学の根幹的な思考図式と言えるのである。
哲学の転回
哲学的思考図式ⅠからⅣへの展開・転回を見て取ると、「哲学」という営みが「その時代」や「その地域」における状況、つまり歴史的な流れとも重なって展開されていることがわかる。哲学の基本的な発想・ルールをまとめよう。
- 全体志向
- 形式的問い
- 方法論的問い
- 一歩、日常の外へ
上記の考え方をもとに、以下のように哲学の問いは変遷していった。
- 「~とは何か」(プラトン)
- 「わたしとは誰か、なにを知りうるのか」(デカルト)
- 問い①×②(カント)
- 「なぜそれを問うのか」(ニーチェ)
ニーチェ以降、当然、哲学思考図式ⅠからⅢもさまざまな角度で見直されているのであって、必ずしも強く「無効」だと言えるわけではない。そんなに単純ではないのだ。しかし、現代哲学はニーチェ的なまなざしを引き継いでいる側面が大きい。さらに、21世紀の哲学はまた違った角度から検討されている。
ここまで「哲学」という枠組みで説明しているが、かつての哲学者たちは、「数学」にも秀でているなど、今ほど専門的な「学問」と限定されていたものではなかった。だからといって必ずしも、みながみな、哲学や数学に親しまなければいけないわけではない。
けれど、そうした事実は押さえておくことで、文系や理系といった極単純なカテゴライズにこだわらなくて済むのではないだろうか。philosophyは「愛智」、つまり「智を愛する」と語彙を分解すると訳されるが、そのように智そのものを大切にする姿勢を、哲学を通じて養う人が増えると嬉しい。