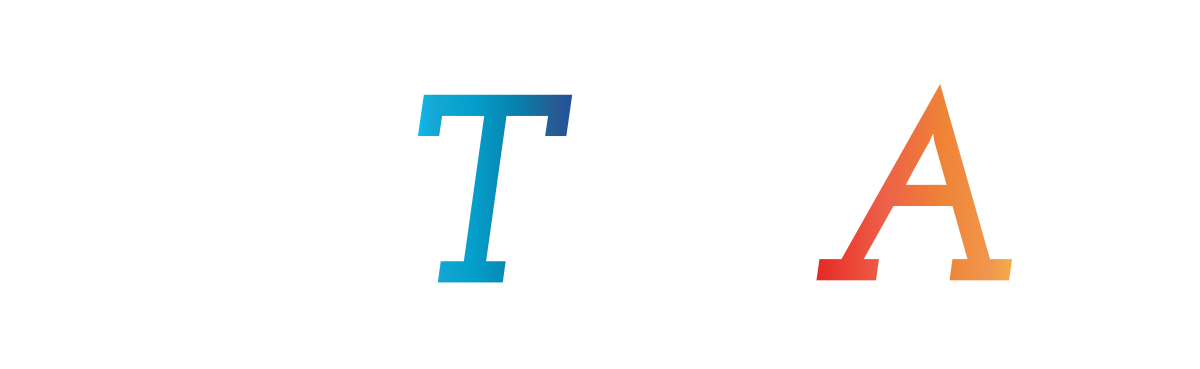この記事では、『話しことばへのアプローチ 創発的・学際的談話研究への新たなる挑戦』(鈴木亮子・秦かおり・横森大輔 編, ひつじ書房, 2017年)に所収されている「創発的スキーマと相互行為的協奏について 「問い」と「相づち」による構造化を中心に」(片岡邦好, 2017)ついて個人的にまとめる。
論文情報
論文概要
本章では、震災体験者のナラティブにみられる「詩的顕現」の過程を検証する。具体的には、ナラティブを誘発するある種の問いかけが、家族の「生還」に暗在する「往復スキーマ」を誘発し、そのスキーマに沿う形で語りが達成されたことを指摘する。さらに、その創発的なスキーマ展開を促進したと考えられる行為に、聞き手の相づちによる構造化支援があげられる。これらの言語・認知・身体的な資源による協奏の下で指標性の重装的な求心的移行が指向され、それらが「今・ここ」において投影する「非明示的テクスト」に注視することで、被災後の意識変化を読み解く手がかりとなることを述べる。
この論文は、震災体験者(女性2名と男性1名、男女ワンペアは夫妻、もう一人の女性は妻側の友人)の語りを言語人類学的アプローチ、特に民族詩学の観点から「明示的/非明示的」に表出するスキーマ(共有・構造化された認識や知識)を分析したものである。特に、3人の語りの話題の中心は「子ども」で(けれども、子ども自体はその会話に一切関与しない)、分析から見出される被災後の意識変化として「親」としてのアイデンティティが揺れ動く諸相と同時に、暗黙理に介在する文化的な「好みとしての傾向」が炙り出される。
この論文の面白みは、「詩的顕現」と呼ばれる、いわゆる「語りにおける絶頂」が立ち上がる様を言語・認知・身体といった多角的側面からあぶり出す巧みな分析的手際さだと思う。こうした分析は、それぞれの領域を横断的・総合的に把握していないと難しい。けれども、片岡(2017)は、即興的に為される会話から微細なレベルで反復する要素を事細かに挙げつつ、語りに暗在する「文化」と呼びうる大きな枠組みとの関係をも捉えようとする。
論文の目次
- はじめに
- 言語人類学における「語り」とその後
2.1 民族誌としての語りの詩学 - データおよび分析の枠組み
- 「震災データ」分析
4.1 スキーマと行為による詩的相同性
4.2 非明示的テクストによる認識的相同性
4.3 考察 - おわりに
論文アウトライン
研究と社会文化的背景は?
2011年東日本大震災の震災体験者の子育て意識について取り組むプロジェクトから抽出したデータを扱っている。特に、「詩的顕現」に着目した分析を行う上で、日本語話者に見られる「好みとしての(認知的・言語使用的)傾向」をも社会文化的な背景として入れている。
課題はどう設定されている?
大震災がもたらした日常の崩壊から、それを回復する際に見られる体験者の語りが、どのような秩序回復として観察・分析できるか、が課題として設定されている。その上で、被災者「個人」としてではなく、被災経験を共有する人々によって共同的に達成される談話的な秩序回復の諸相を捉えることが目指されている。
1と2に即した理論と方法論的位置づけはどうなってる?
「詩学」の実践に該当す“poem”は、「創作」にあたるとし、混沌から秩序を作り上げる詩的実践を捉えるために、「民族詩学(ethnopoetics)」を理論・方法論として取り上げている。一方、民族詩学を切り開いたHymesなど(バース/スタンザ分析)を挙げつつも、その構造主義的分析(分析をする研究者にとって特定の構造的前提を持ったもの)の問題点も指摘する。特定の前提を持たずに即時的に為される相互行為分析として会話分析を挙げつつ、そのような相互行為にも「定型的な語り」に収斂していく現象もあることを指摘する。そこで、定型的な語りを分析するために、語りの中で際立つ音調的輪郭や語彙密度の増加、比喩、反復、平行性などの修辞的特徴が、語りの中の「絶頂/クライマックス」として強調的に浮き上がる「詩的顕現」をあげる。
パース記号論を出自とし、社会記号論系言語人類学で特に取り上げられる「指標性」を起点に、談話の要素とその連鎖が連なる諸相も分析される。特に、形式的文法(特に動詞)における指標性の大小(小:述語動詞 > アスペクト > テンス・モダリティ > ムード:大)、語り手の介入度の階層(小:直接話法 > 自由間接話法 > 間接話法 > 発語行為報告 > 行動報告:大)に着目した分析となっている。特に、認識動詞「わかる」「〜と思う」が語りの中で配置される際、特有のリズム(好みとしての型の傾向)として表出し、「小さな語り」に表出する(子どもの)「出発(登校) – 帰還(帰宅)」の認知スキーマとの関連を分析する。
事例データと分析の妥当性は?
インタビューでは、「子どもを育てていて震災の前と後で意識の変化があったか」(上位トピック)を質問し、それに対して以下の下位トピックが挙げられた。インタビューに対する語りは、日々の体験談や報告から成り、「小さな語り」が集積していたと捉える。
- 食べ物への気配り
- 登校時の見送りと帰宅への不安
- 不足の事態への対処法
- 男親・女親の認識の差
細かいデータ分析の部分は省略。「4.3 考察」では、「ことばと真意は裏腹でありうる」ことを冒頭で指摘するように、「語り手の意味内容が発話者の意図を直接的に反映する」といった安易な分析は避けようとしている。その上で、微細な語りの分析から浮き上がった特徴を、「1から4」に至る過程を俯瞰的に捉え、以下のように分析する。
指標性が高いとされる言語使用(引用、スキーマの暗在)に着目すると、言及指示対象がほぼ一貫してオリゴに収束する形で、つまり「発話/行為」から「思考」へ、「外」から「内」へ、「往」から「復」へと向かって、体系的な相同性と求心性を示す。
これを総括し、相互行為の分析と、それを取り巻く文化的な傾向が収斂して表出する諸相、ならびに「(インタビューの)問いかけ」が引き起こした「出発 – 帰還」イメージといった複数のレベルの要素が、ある種、語りを通して弁証法的に立ち上がることを指摘する。詩的構築という観点から文化的制約や共有されるスキーマの制約がマクロな条件的適切性に寄与した研究は少ないことも指摘する。こうした重層的な参与者間の相同性と反復的求心性が、自己肯定感の回復・強化としてつながっているのではないかと考察する。
今回の語りが参与者によって共同的に達成されることで、一定程度、共有する出来事や認識を確認し合い、語りによって混沌から秩序が生み出され、「回復」として作用することは大いにありうると思う。一方で、それがその参与者の日常にとって、「どのような意味を持つのか?」は、即時的な語りの分析のみだけでは見出されない。ここでの分析は、あくまでもインタビューアーが震災体験者と出会したことで起きた非日常的な出来事であり、実際の「日常レベル」でどのような形で関係が作られているかは、推測することしかできない。そのため、やはりあくまでも「出来事レベル」で、今回の分析が見出したような「非明示的テクスト」が表出したといえる。つまり、インタビューアーの介入によって、非明示的な意識が炙り出されたということだと思われる。その意味で、半意識的だったものが語りを通して言語化され、また共有されることで、「回復」らしきものが垣間見えたと言えること自体は、妥当ではないかと思う。
論文における今後の課題や展望はなに?
一方で、このような語りは単なる「回復」だけではなく、分析にもあるように個々の認識や価値観に「ズレ」があることも浮き彫りだったことにも、個人的には注目したい。基本的に、突き詰めれば個々には当然、ズレがあるのが自然で、語りを通してそれが明らかになり、また詩的顕現として表出することもあると思うからである。分析者が前提として何かしらの認識(今回で言えば、文化的な好みとしての認知的・言語的傾向など)があるのもまた避けようがないことなので(でなければ研究に取り組むことは難しい)、その認識を相対化しつつ、「実際に何がどのように為されて、どのような作用をもたらしているか」を探る手立ては、丁寧に考える必要があると感じた。
自身の研究における関連性や引き継ぐ議論はどんなもの?
今回は「会話」、特に制度的会話である「インタビュー」データであった。個人的には、デジタルメディア上の言語コミュニケーションを追うことが多く、分析概念として「小さな語り」、「詩的顕現」、「スキーマ」は援用したいと考えた。特に、デジタルメディア上では、必ずしも日常的に関係を持つ人々同士のやり取りばかりではなく、突発的に起きる出来事(調和・不調和)が数多くある。また、そのデジタルメディアで特有の共同性を持つ人々に暗在する「好みとしての傾向」は、嗜好性に依存し、またその嗜好性を持つ人々が関与するジャンルなど、多様である。そうしたメディア環境的特徴や文脈に注意しながら、代表的に見出される(文化的、もしくは社会的)「結束性」が生まれる出来事を捉えることは試みたいと感じた。
次に読むべき書籍や論文は?
- Leach, Geoffrey, N. and Michael Short. (2007) Style in Fiction, London: Longman.
- Friedrich, Paul (2001). Lyric Epiphany. Language in Society 30 (2), pp.217-247