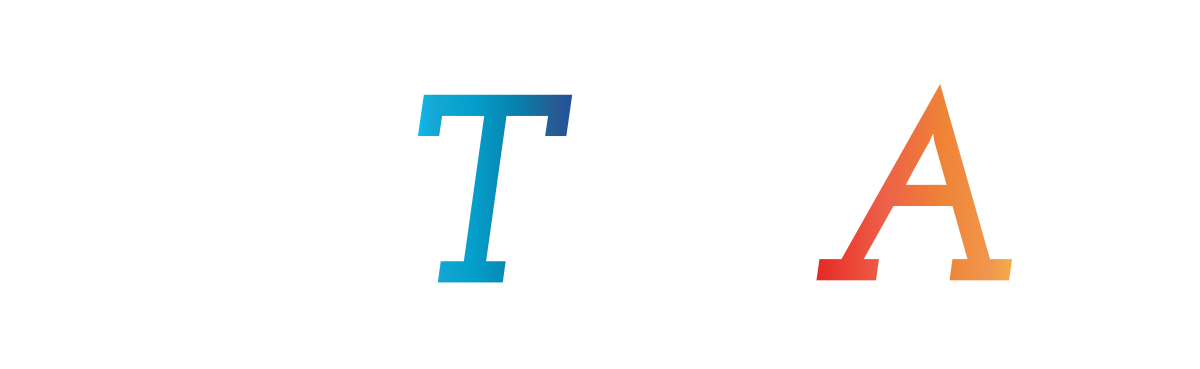本記事では、2024年5月に合格した博士論文「自己責任ディスコースの言語人類学的研究──中東地域日本人人質事件を題材に」の終章全文を掲載する。すでに序章の全文は公開していて、ふと思い至って終章も公開することにした。
終章 「自己責任」はどう語り直せるか
本稿では、自己責任ディスコースが日本社会で生成・再生産されるメカニズムを分析・考察してきた。具体的には、序章では、第一に日本社会で自己責任論はなぜ・どのようにして繰り返されてきたのか、第二に自己責任論の分析から日本の自己と責任の文化モデルを分析的に抽出することに問いとその目標を焦点化することを示した。
第1章では、「自己責任」に関する西洋文化圏と漢字文化圏の対照的な関係を指摘し、特に日本社会では自業自得とも解釈・主張される懲罰的な自己責任論の事例を整理した。「自己責任」という文字記号に着目すると、複数の意味解釈・主張が投影される過程が見出せる。そこで、記号的な言語コミュニケーション実践に着目する言語人類学の観点から自己責任ディスコースを分析した。
第2章では、言語人類学の研究アプローチや関連する思想哲学を整理し、メタ語用論的な観点から欧米文化圏の語用論やメディア研究のイデオロギーを論じた。簡単にまとめれば、これまでのディスコース研究では「差異」を基調として議論が展開されている。しかしながら、本稿では自己責任ディスコースに投影される「差異」と「類似」の表裏の関係に着目する必要があることを示した。
第3章では、全国新聞五紙を手がかりに日本社会で自己責任ディスコースが語られてきた歴史を記述的に分析した。特に着目したのが、語りやすい言説と語りにくい言説の相違である。これまでは、自己責任論は新自由主義イデオロギーの一環としてリベラル派から批判的に論じられることが多かった。一方、自己責任の言説史を追跡すると、むしろリベラル派もまた個人の自由を尊重する自己責任を肯定的に語り、また保守派は社会変容に対応する統治の論理として自己責任が積極的に語られていた。さらにこうしたなかで、「迷惑」という用語が「自己責任」とともに使われるようになったことが確認された。
第4章では、自己責任論を日本社会に広めるきっかけとなった2004年のイラク日本人人質事件の事例分析を行った。人質3名とその家族に対し、世間を騒がせたことに対し「迷惑」をかけているという論調が自己責任論の理由づけに用いられていた。国家主義的な保守派にせよ、市民性を重視するリベラル派にせよ、人質らの「迷惑」に関しては否定しがたい規範として共有されていたものだった。
第5章では、2015年のIS日本人人質事件でもインターネット上に表出した自己責任論と迷惑の主張を手がかりに、文化的規範がどのように投影されているかを分析した。分析によると、外部の国家・家族・職業といった対人関係・役割規範に基づいた自己責任論が人質に寄せられていた。つまり、自律的個人を基調にすると解釈される自己責任論は、日本社会においては外部の他者の視点を経由しながら論じられる傾向があることを見出した。
第6章では、自己責任論に関連しつつも積極的に分析されてこなかった日本の文化規範に着目し、自己観と責任観の相互的な関係性の分析と考察を掘り下げた。特に着目したのが、欧米的な個人観を「自己が責任をとる」としたら、日本的な個人観は「自己における責任がある」という場・基体を経由している点である。言語人類学的な談話研究では、メタ語用論的な分析によって単なる解釈ではなく、相互行為上のパターンが生じるメカニズムを自己観として論じてきた傾向にある。一方、談話研究では自己観に着目しても、責任観に関わる権力の問題などは背景化される傾向にあった。また、社会学やメディア研究では権力の問題を論じても、言語学的分析は背景化されてきた。
本稿では、言語人類学的観点から自己責任ディスコースに関わる責任観を中心に分析を掘り下げた。特に、懲罰的な自己責任論が生じるメカニズムに関わる自己犠牲の論理に着目し、責任が強く認識されるからこそ、そこから逃避・蓄積する「自意識」の形成を指摘した。つまり、日本的な自己観と責任観を考慮し、集団的な連帯性と個人的な無意識・意識の相互関係を分析する方途について、本稿では自己責任論と自己犠牲の事例からそれを示した。最後に、総括として近代社会秩序とその理性主義的・個人主義的な論理が逆説的に責任を無化してしまうことに関する社会学的分析と、「迷惑」の文化規範と権利が衝突・交叉する日本の人類学的分析を整理した。
自己責任ディスコースが日本社会で生成・再生産されるメカニズムは、「自己責任」という文字記号に、語りやすい/語りにくい複数の記号イデオロギーが関わっていることにある。具体的には、近代社会における社会契約的な「個人」、日本における新自由主義≒新保守主義と市民性といった自由と統治の入れ子関係、さらには日本の言語文化イデオロギーとしての「世間」を媒介にした「個人」の意識などが挙げられる。本稿では、自己責任ディスコースの系譜的読解と象徴的な事例として中東地域日本人人質事件を言語/記号人類学的に分析することによって、上述した複数の記号イデオロギーの入れ子関係を紐解いてきた。特に、保守系とリベラル系のイデオロギー的差異を踏まえても暗黙理に否定しがたく共有されてしまっている文化規範が関わっていることを見出した。本研究では、各々の政治的イデオロギーに還元されてきた自己責任ディスコースに対し、むしろ政治性を相対化し、関連する文脈を記述的に明らかにすることで、「自己責任」に対するイメージを更新する手がかりを見出してきたものといえる。つまり、本研究が行ったのは自己責任論の問題解決ではなく、問題に向き合うためのアプローチを示したことにある。
本章では、最後に本研究の意義と含意についてまとめたい。まず、言語人類学的研究に対し、本研究は日本の自己責任ディスコースを事例に自己観と責任観の関係を分析する方途を示したことにある。これまでの言語と相互行為に焦点を当てたディスコース研究では、変容する社会に応じて、調和と共生を重視する研究と、不調和と権力を重視する研究に二分される傾向にあった。前者の代表が場の言語学、後者の代表がCDSや社会記号論系言語人類学である。特に、前者では対人的な友好関係による連帯を重視する。後者に関しては、CDSは権力分析による個人主義へと回帰するかイデオジカルな主張が展開される一方、社会記号論系言語人類学では理性主義的・近代主義的な言語構造/使用のメタ分析に特化する傾向にある。これら研究潮流に関わる自己責任ディスコースの言語人類学的研究を遂行した本研究は、それぞれのイデオロギーをメタ分析して相対化しつつ、Gal & Irvine(2019)の差異/類似の記号イデオロギー論を踏まえて研究上のイデオロギーに還元しない分析と考察の方途を示した。
特に、本研究において重要なのが、ポストモダン社会の状況・条件を分析と考察の視座に含めてきた点にある。1990年代はじめに起きた冷戦崩壊、あるいはバブル経済崩壊以降に言及されてきた「失われた30年」は変容する社会とその改革の失敗を示し、その過程で政治的なシンボルとなったのが「自己責任」である。文字記号としての「自己責任」に着目することで、自己責任ディスコースに投影される複数の解釈や歴史・社会文化的な文脈を紐解いてきた。特に、自律的個人や新自由主義的主体を指標すると思われてきた「自己責任」は、日本社会において伝統的な文化規範とも結びついてきた逆説的な展開を見出した。いわば、プレ/モダンが衝突・交叉するポストモダンの状況を浮かび上がらせるのが自己責任ディスコースであったと総括できるだろう。
現代思想では、冷戦崩壊を機に特定の政治信条や世界観を信奉する「大きな物語」が衰退し、複数の主体による複数の解釈が「小さな物語」として跋扈すると論じられてきた。本稿では直接的な言及は多くないものの、複数の記号イデオロギーを分析・考察する念頭にあったのは「ポストモダンの条件」を読み解くことにある。本研究では、社会記号論系言語人類学の近代主義的なイデオロギー性を批判的に捉えつつも、言語人類学的な詩学などを援用し、動的に形成される複数の構造パターンを記号イデオロギーとして分析してきた。言語構造/使用に投影される歴史・伝統と新たな文脈の創造の二重性を分析する言語人類学は、複数的な記号イデオロギーのパターンを分析する上で有用な研究アプローチを持ち得る。本研究は、自己責任ディスコースの言語人類学的分析により、ポストモダンの条件を炙り出した研究である。
一方、できる限り自己責任ディスコースを相対化してきた本研究にも方法論的な限界がある1。特に、あくまでメタ的な視点で歴史的な「分析」を行ってきたため、個々具体的な出来事において問われる「責任」に対する価値判断やその理論づけを論述してきたわけではない。また、パース記号論とそのプラグマティズムの格率に則って経験的研究を遂行してきた言語・相互行為研究からすると、本研究は非実証的で多分に解釈的なものに映るだろう。しかしながら、複数の記号イデオロギーがまとわりつく自己責任ディスコースを言語人類学的に研究するためには、本稿がとったアプローチをとることがほとんど限られた方法であった。
最後に、ディスコースを仔細に分析する言語人類学的研究から離れるものの、本研究に基づいて「自己責任」を語り直す方途について考えたい2。「自己責任」のイメージを変える例として取り上げたいのが、イラク日本人人質事件で人質となった今井紀明氏が帰国後の会見で語った内容である。今井氏はその会見で、「自己責任論、自業自得と言われているが、僕自身は信念を持ってやっている。そうやって言われるのはとても心外です」と語っていた。本稿で着目したいのが、今井紀明氏の失敗とその後に示した信念である。
本稿では分析的に論じてきたため言及してこなかったが、端的に言えば、二つの中東地域日本人人質事件において人質となった人々は「失敗」したと考えている。ゆえに、人質に一切の「自己責任」がないとは筆者は思わない。しかし、「自分だけの責任」として人質らの行為を否定したり、社会から排他したり、スケープゴートとして処したりしてもいいとは思わない。ここで言う「失敗だった」とは、人質となってしまったことに尽きる。危険地域だろうと渡航してもいい。移動の自由の権利は人々にある。だが、それは人質となった被害者自身も「人質とならなくてもよかった」、少なくとも「ならないほうがよかった」はずで、その意味で「失敗」だった3。
一方、人質となった当時18歳だった今井氏は、帰国後のバッシングの影響で対人恐怖症を患いつつも自身の「失敗」を訂正する活動を続けている。たとえば、住所が記載されたバッシングの手紙に返事を出し、その女性と直接会った経験が新聞で語られており、「ある女性は『働かず、好きなことばかりする若者が腹立たしい』」と書かれたものの、「手紙のやりとりを続けると、4通目で『色々な事情があって、今井さんもやりたい道があるのでしょう。がんばってね』と励ましに変わった」という4。2012年には自身の失敗経験から孤立する10代を中心に支援するNPO法人「D×P」を立ち上げ、地道な対話を続けている。
多くの非難が懲罰的な自己責任≒自分だけの責任を求め、その非難を受け入れることも自己責任≒覚悟だと論じていたとすれば、ここでその非難を別の形で引き受けるのは自己責任≒自分にしかできない責任、つまり自己責任≒信念へと訂正してきたものだと言えるのではないだろうか。ここで着目しているのは、自己責任≒信念そのものを単に肯定しているのではなく、生きる過程で出くわす失敗を引き受け直すという、その訂正をし続けていく固有性である。したがって、その訂正から見出せるのは確固として自律/自立した「個人」というよりも、むしろ自身の信念や失敗と他者からの批判や規律の二重性を引き受ける「固有性」である。これを少し抽象化して言い換えれば、生きるということは「この私」と「キャラ」の二重性を引き受け直すことにある。こうした偶然と必然の交叉からやってきてしまう二重性の複雑さを引き受けることなしに、「責任をとる」ことを考えること、あるいは遂行することはできない5。
今井氏の例をはじめとした失敗など、人間が行った行為やその姿勢の是非はまた別途、考えるしかない。少なくとも、今井氏の姿勢が見せたように、自己責任≒自分だけの責任を求める人に、自己責任≒自分にしかできない責任を提示しながら訂正をし続けて対話の可能性を見出すこともひとつの手立てだろう。
一方で、「自己責任≒自分にしかできない責任」という主張は、困難に陥っている相対的な弱者の人々に能力主義を押しつける言説に還元して理解されてしまうかもしれない。なぜなら、結局のところ、他者が他者の「自己責任」を要請する言説と類似した構図となってしまっているからである。だが、筆者が自分にしかできない責任として自己責任を示したいのは、むしろ、人間が自らを絶えず訂正し続ける孤独さである。
これまでの自己責任論では、社会的な弱者を追い詰める排他的な言説に対し、他者を大事にするべきだと論じられてきた。しかしながら、そこで想定されているのは他者を大事にする「わたしたち」であって、必ずしも「わたし」ではない。言い換えれば、公の場における排他的な自己責任論に対し、公共的な倫理によって批判しているが、私的な実存は捉えられていない。確かに、排他的な自己責任論は問題だが、それを批判すること自体が特定の公共性に依拠している。つまり、誰かが誰かの責任を主張する構造自体はどちらも「同じ」である。ある意味で、自己責任論は日本社会が陥っている言論の機能不全をも象徴している。
だが、今井氏の「信念」と「対話」を示す例で見られたように、人間社会には常に特定の思想信条に還元しきれない余剰が存在する。そもそも、「ことば」自体、現実を不完全にしか反映しきれない。したがって、記号的な言語・コミュニケーション実践に時間的・空間的なズレが伴うことからは、記号に回収しきれない余剰をいかに見出すかという問いへと展開することができる。誰しもが「責任」を語ってしまっては、むしろ「責任」が無化されてしまうことを本稿では見出した。したがって、「責任を果たす」ためには「無責任」であることの価値も訴えなければならないであろう。
おわりに
実は、終章ではもっと哲学的な議論と、とある文学読解も関連づけて展開する予定だった。だが、博士論文としての論旨をわかりやすく提示してほしいとのコメントを受け、内容をシンプルにしたものとなっている。
ただ、博士論文で援用する言語人類学に対する批判的論点、また論理展開において意識していた東浩紀の哲学についてなど、「記号」や「責任」を原理的に考える残滓のような内容は脚注に残っている。中途半端ではあるものの、断片的だからこそ、今後書き直す可能性が高い。なので、Web記事として公開してもいいだろうと判断した。
博論で、「結局、青山は自己責任論をどう捉えているのか」を論じられなかったことをとても残念に思っている。書き終わったいまでもそう思う。本当はもっと「哲学」として論じたかったが、構成の都合上、徹底して記述的に語らざるを得なくなってしまった。悔しいというか、諸々の状況のなかでやり切れなかったことを苦々しく残っている。書籍化した暁には、ぼくが考える自己責任論も論じたい。なので、終章自体はかなり書き換える予定で、ある程度、新たな方向性も見定めている。今度は下手な後悔をしない内容に書き上げたい。
序 章 いま、自己責任論を問う意味
第一章 自己責任論はどう語られてきたか
1.1 自己責任のメタ意味論
1.2 自己責任論と自業自得
第二章 言語人類学的研究
2.1 言語/記号人類学
2.2 メタ語用論とインターフェース
2.3 記号、言説、批判
2.4 小括
第三章 「自己責任」の言説史──全国新聞五紙を中心に
3.1 分析データとその方法
3.2 全国新聞五紙における自己責任ディスコースの変遷
3.3 1980年から2003年の言説史
3.4 考察
3.5 小括
第四章 イラク日本人人質事件と戦後民主主義
4.1 イラク日本人人質事件とは
4.2 分析手法
4.3 イラク日本人人質事件のディスコース分析
4.4 2004年から2014年の言説史
4.5 小括
第五章 IS日本人人質事件と世間
5.1 IS日本人人質事件とは
5.2 分析概念と手法
5.3 IS日本人人質事件のディスコース分析
5.4 考察
5.5 小括
第六章 自己責任ディスコースの文化論理
6.1 自己−責任の文化的インターフェース
6.2 自己責任ディスコースの生成・再生産メカニズム
終 章 「自己責任」はどう語り直せるか
参考文献
東浩紀(2019 [2015])「デッドレターとしての哲学」『現代思想 2015年2月臨時増刊号』青土社, 東浩紀『テーマパーク化する地球』pp. 187-232. ゲンロン.
───(2023 [2017])『観光客の哲学 増補版』ゲンロン.
Gal, Susan & Irvine, Judith T.(2019)Signs of Difference: Language and Ideology in Social Life. New York: Cambridge University Press.
石田正人(2015)「プラグマティズムの暗い背景 C・S・パースの場合」『現代思想』43(11): pp. 45-53 青土社.
今井紀明(2004)『ぼくがイラクへ行った理由』コモンズ.
パース, C. S.・ジェームズ, W.・デューイ, J. 植木豊訳(2014)『プラグマティズム古典集成』作品社.
- 自己責任ディスコースが示す個人・社会の関係など、本稿では語りきれなかった論点も多い。特に、AI技術が発展した現代では、新たな記号観が主導的になっている現実、またAIによる社会や文化への影響なども挙げられる。そもそも、本研究がポストモダン社会の状況として論じてきた個人化は、日本における1990年代のインターネット環境/技術の一般家庭への普及や、カリフォルニアで発達した情報技術と独特の思想とも大きく関係している。 ↩︎
- 言語人類学をはじめとしたメタ語用論研究の核には、C・S・パースが提示したプラグマティズムの格率を背景とした独特な「信念」が関わっている。その信念とは、記号的な知の「意味の確定」を未来的な行為帰結主義として前進するプラグマティズムの方法論的アプローチのことを指す(植木 2014:577)。パースは自身のプラグマティズムの立場を、スコットランド常識学派の成果と結びつけ、それを批判的常識主義として再定立している。その批判的常識主義は次のようなものを指す。信念や知の確定化過程は確定状態と不確定状態の間にあり、たとえ確定できなくともいずれ確定できうるものであるならそこで可能的に作用する条件を考えればいい。したがって、パース的なプラグマティズムが依拠するのは「未来を見据えた今現在」で、ここには独特の記号作用とその条件に関わる知的な時間論が挟み込まれている(ibid.: 599)。
パース的な経験的研究は、誤りやすい、あるいはすべては記号過程のなかにあると自認する「探究者」が「いまここ」で見出す記号的実態の研究となる。したがって、そのパース的なプラグマティズムの格率を自認し、それぞれの「いまここ」を共有する共同体による研究が遂行される。こうしたパース的なプラグマティズムの発想と、第6章で論じた西田哲学的、あるいは場の言語的な経験的・場的な発想は「いまここ」性への焦点化という意味では相似している。ただし、前者のパース記号論は可謬主義的・科学論理的な発想を中心にその理論を立脚する一方、後者の場の言語学では再帰的な創発性を中心に言語と主体の理論を立脚する。両者にまたがる言語人類学的な議論は、確かに文化的な古層を言語の構造的・累積的・認識的な痕跡から見出そうとするものだが、この両者ともに時間的なズレを伴った「記憶」の論点はテクスト化とコンテクスト化へと還元される傾向にある。
ここで疑問なのが、果たしてこれは「常識」だと言えるのだろうかという点だ。確かに、あらゆる記号の無数の散らばりをなるべく明晰に見出そうとするのがパース記号論である。その意味で、あらゆるヒト・モノ・コトの実態に接近する術をこの方法は提示している。しかし、あくまでその方法(可謬主義、プラグマティズムの格率、記号過程)を共有する人々にとって見出される知である。パース的なプラグマティズムの格率に暗い背景を読む石田(2015: 52)は、「科学の探究において発生する知的かつ抽象的概念のために格率が提唱されたのであって、任意の概念・言葉・記号に対する格率の適用が推奨されているのではない」とこの方法論の「秘密」を指摘している。 ↩︎ - 加えて言えば、その会見では「謝罪」をせずに、今井氏は「事実」を粛々と語ったというが、その詳細は現在確認できないものの、社会的なバッシングを加熱しすぎないような対応もまた必要だったと考える。今井氏は自著の『ぼくがイラクへ行った理由(わけ)』(2004: 110-113)にてその経緯を記しており、会見後の高遠氏との電話にて「人の道として謝らなければいけない」と強く主張され、謝罪してもよかったと思い返していることを述べている。 ↩︎
- 朝日新聞朝刊「(考・民主主義はいま)バッシングの嵐、話せば伝わる イラク人質、今井さんのいま【大阪】」(2014年2月7日) ↩︎
- 東浩紀は、人間の誕生を司る「家族」の関係を偶然と必然の交叉から考えている(東 2023 [2017]: 260-262; 2019 [2015]: 229-231)。偶然と必然の交叉の例に挙げられるのが親子の非対称な関係である。たとえば、親にとっては子が「その子」であることは偶然だが、「その子」にとって「その親」であることは必然という非対称性がある。さらに言えば、「その子」にとって「その親」が暮らす「その地域」や「そのアイデンティティ的出自」も事後的な必然として見出される。偶然と必然は一方からのみ考えられず、その交叉は誰かにとっての必然は誰かにとっての偶然という非対称的次元、つまりインターフェースで生じる。これは出生をめぐる家族だけではなく記号の次元でも生じる。たとえば、この論考における文章やどこかの会話が活字となり、それを受けた人が新たな出来事を起こすのも誰かにとっての偶然が誰かにとっての必然へと事後的に転化して見出される。
ヒト・モノ・コトの邂逅とその界面には、複数の主体による事後的な出来事によって見出されるズレ(=誤配)が潜在している。つまり、必然性は後から遡行的に見出される。この遡行的にしか見出されない必然性を受け入れること、それが「責任をとる」ことでもある(ibid.: 231)。言い換えれば、それは無責任であるなかで生じる責任を引き受けることであり、はじめから定立された必然的な「責任」はむしろ偶然と必然の交叉を忘却したものだと言える。難しいのは、思いがけず出くわす責任を引き受けることであり、その忘却は「責任がある」ことを論じる安直さと逆説的な責任の無化にも通じる。 ↩︎