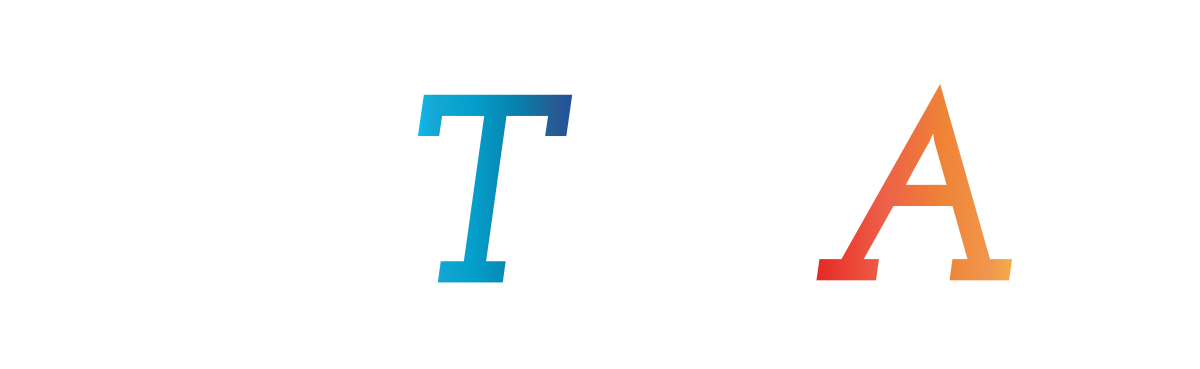国際政治学の分野で言説分析を用いた研究を行う先輩に「自己責任」のディスコース研究をしていく上での相談をしていた際に紹介してもらった仁平典宏(2011)『「ボランティア」の誕生と終焉 <贈与のパラドックス>の知識社会学』を読み終えた。広義のディスコース研究の理論・方法論の視座を勉強しつつ練り直そうとしていた自分にとても勉強になる本だったので雑記として簡単にまとめる。
本書で用いる方法論は「理念史でも言説分析でも構築主義でもない」、これまで「この研究は◯◯ではなく~」という否定形で現れる「(弱い)知識社会学」である。ややもすれば、言説分析も知識社会学もその射程で捉えようとする「イデオロギー」や「権力」といった問題は、社会的な事象を「客観的」に捉えていくことを志向すればするほど、その「不可能性」にさいなまされる分野でもある。「概念」や「語られたもの」を分析するというのは聞こえはいいが、どのように理論(存在論・認識論)・方法論(リサーチデザイン・手法)を整理するか、また調査を行い、それらを論理的な一貫性を持ってまとめられるかはそう簡単なものではなく、そうしたことを怠ると”なんでも”言説分析もしくは知識社会学になってしまう。
橋爪(2006)は、言説分析や知識社会学“それ自体”も「言説」や「知識」として述べられていることでフーコーがどこまでも分析されるメタなレベルの言説なのかをはっきりとさせていないとし、言説分析は理論を持ちえず“発見的”な方法であることを指摘している1。
佐藤俊樹・友枝敏雄[編](2006)『言説分析の可能性 社会学的方法の迷宮から』
橋爪大三郎(2006)「第6章 知識社会学と言説分析」
では、仁平(2011)は「ボランティア」を社会学として研究していくにあたって、どのようにして「(弱い)知識社会学」を捉えていったのか。本記事では、『序章 「ボランティア」をめぐる語りと<贈与のパラドックス>―問題設定と方法』を中心に、(社会記号論系言語人類学/批判的談話研究を学ぶ)筆者の問題意識と合わせてまとめる。
『「ボランティア」の誕生と終焉』の構成と目的
『「ボランティア」の誕生と終焉』の目次
序章 「ボランティア」をめぐる語りと〈贈与のパラドックス〉—— 問題設定と方法
第Ⅰ部
第1章 「ボランティア」のささやかな誕生—— 戦前期日本における〈贈与のパラドックス〉解決の諸形式
第2章 戦後改革と不分明地帯の再構築—— 1945~1950年代前半
第3章 〈政治〉と交錯する自発性と贈与—— 1950年代前半~1960年
第4章 分出する「ボランティア」—— 1959~1970年
第Ⅱ部
第5章 「慰問の兄ちゃん姉ちゃん」たちの《1968》—— 大阪ボランティア協会とソーシャル・アクション
第6章 國士と市民の邂逅—— 右派の創った参加型市民社会の成立と変容
第Ⅲ部
第7章 ボランティア論の自己効用論的転回—— 転換する「戦後」:1970年代
第8章 実体化する〈交換〉・忘却される〈政治〉—— 1980年代
第9章 「ボランティア」の充満と〈終焉〉—— 互酬性・NPO・経営論的転回:1990~2000年代
終章 〈贈与〉の居場所—— まとめと含意
『「ボランティア」の誕生と終焉』の目的
冒頭でこの書の目的は下記のようにまとめられている。
本書は、「ボランティア的なもの」に関する語りの形式が、明治期後半から2000年代にかけてどのように変容してきたかについて分析し、それを通して、現在の政治的・社会的環境の特徴の一端を明らかにすることを目的とする。
「ボランティア」の本質を追求するのではなく、「ボランティア的なもの」に着目して「ボランティアとは何か、どういう価値をもっているか」について「これまで人々は何を語ってきたか」に注目し研究を行っている。ボランティアの”語り”に関するメタ的な分析がテーマだという。
ここでいう「メタ」とは二つの分析的意義を含んで用いられている。
- 人々がボランティアをそのように捉えることが、いかなる政治的・社会的文脈で行われ、どういう帰結とつながっているのか。
- →「動員モデル」の理論枠組の検証((社会主義の崩落に伴って浮き彫りだった参加型市民社会は「経済的グローバリズム」や「ネオリベラリズム的秩序」に奉仕するように構成されており、ボランティア活動が「自発的」に行われることは行政コストを減らし社会に適合的な「主体」を用意してしまうことで新たな管理形態を支えるものだとすると指摘した中野敏男(1999)『ボランティア動員型市民社会論の陥穽』の議論により、市民の「動員」という問題系に関する理論的枠組が進んだという。))
- ボランティアの言説において繰り返し現れるパターン(意味論形式)の抽出
- →ボランティア言説固有のコードを解き明かす鍵((「動員モデル(国家や資本の要請)」だけでは説明しきれない、ボランティア的なものの語りに現れる「肯定/否定」、「称揚/冷笑」のパターンこそがボランティア言説において現れることばのやり取りを説明する上での鍵になるとする。))
新聞で用いられる見出しなどを調査し、「ボランティア」ということばが2000年前後から縮小している(第9章)ことからも、単に動員モデルからボランティアの増加を説明するのではなく、縮小するにいたった別の要因があるのではないかと捉え、近現代の日本で「ボランティア」の言葉が「誕生」し、ある意味で「終焉」を迎えるに至った過程を分析することを、この書の主要な目的としている。
贈与のパラドックス―「ボランティア的なもの」と「動員」との関係を探るために用いる補助線
仁平(2011)は「肯定/否定」や「称揚/冷笑」といったコミュニケーションを創発させるボランティア固有の意味論形式があり、それらは政治的左右に関わらず「ボランティア的な善意の活動」を「逆説」で語り得てしまうことを指摘し、ビートたけしの「ボランティア」に関する下記の見解を引用する。
(阪神淡路大震災やナホトカ号重油流失事故時のボランティア活動について)「個という意識が確立されてないないこの国では、周りが行くと言った時に『俺は嫌だ』と言えないんだね。まして”善意”の人には逆らえない。それで、やらない奴は自然に村八分の状態になったりすることになる。」「ボランティアにあらざれば人にあらずみたいな風潮は嫌になるね。」(ビートたけし 1997:78, 80)
「ボランティアという行為には、そもそもすごいパラドックスがあるんだよ。国のやる福祉というのがそもそもボランティアだろう。大震災の被災者の世話でも、重油を肥柄酌ですくうことにしても、本来は全部国の仕事のはずだ。そういった事件が起きたときのために、普段から高い税金を払ってあれだけたくさんの役人を養っているわけなんだから。だからボランティアをやればやるほど、本来働くべき人間に楽をさせ、間ぬけな国を助けていることになる。そのことに、どうしてみんな気が付かないんだろうなと思うね。」(ビートたけし 1997:86)
ビートたけし(1997)『ボランティア亡国論』、「新潮 45」16(3)、新潮社 P78-87
ボランティアに限らず、参加型市民社会においてなされる様々な事柄は「善意」や「他者のため」と解釈されてしまうことを不可避的に含んでしまう。このような「他者のため」と外部から解釈される行為の表象を<贈与>と定義し、行為者や発話者といった当事者が「善意」を意図している/いないに関わらずに成立することの重要性を説く。
この「贈与」の意味論形式が成り立ってしまうことが市民社会やボランティア言説に関わる得意なメカニズムとして機能していることが、この書で貫かれている仮説であるという。ボランティアの実態がどうこうという位相の議論ではなく、必然的に関わり解釈をほどこし、その上で「ボランティア的なもの」に関わるコミュニケーションを誘発する第三者が<贈与>なる定義を構成していることを指摘する。
こうした解釈性は<贈与>に限らずあらゆる行為にも言えるが、<贈与>には行為者の「意図」の問題を浮きぼり立たせるものの、「真の意図」には到達することができないという不確定性が常につきまとうことをその特徴としている。
さらに、<贈与>には対概念である<交換>の意味もつきまとう。なにかを行ったからすぐになにかが返ってくるといった単純な交換ではなく、遅れを含んだ返礼を伴うのが<贈与>における<交換>の関係である。つまり、なにか「他者のため」という行為がたとえ返礼を求めないという意図を行為者がもっていたとしても、受け手が感謝をはじめとした反対贈与をもたらすものである以上、純粋な贈与にはなりえない。
上記の議論を哲学者デリダの否定神学的な論述をあげ「(純粋な)贈与の不可能性」を説明した上で、社会学的に捉えると、<贈与>は常に<交換>とにおける連続的な意味論形式を持つという、不安定な存在であることを指摘する。このような意味的な関係をもたらしてしまうことをこの書では<贈与のパラドックス>と呼び、分析を一貫づけるにあたっての仮説であるとする。
こうした区別は単に実体的なボランティアを追求するのではなく、あくまでも「ボランティア的なもの」を成り立たせている言説の位置づけに迫るために用いる補助線でもあることがポイントだろう。<贈与のパラドックス>という補助線を基準に持つことで、その不安定な「ボランティア」にまつわる人々の語りやそこで表出する葛藤に伴う意味論形式の変化と、さらにそれらが動員という現代社会における問題系とどのように関わっているかを検証していくことを可能にするというわけである。
(弱い)知識社会学―理念史でも言説分析でも構築主義でもない方法論を求めて
上述してきた「ボランティア的なもの」に関する<贈与のパラドックス>をはらむ意味論形式と参加型市民社会における「動員モデル」の検証という課題を持つこの書は、これら二つの課題において「メタ」であることが目指されている。しかし、二つのメタ分析は研究を一貫性を伴った論述を施す上での認識論/方法論的な折り合いの悪さがどうしても露呈してしまう。
というのも、動員モデルでは言説を位置づける社会を素朴に想定する一方で、意味論形式の分析は「社会」と「言説」の関係を二項対立的には捉えない。そのため、既存の社会学研究における方法論を素朴に用いることはできず、「~でない」という否定を積み重ねる中で方法論を策定している。そこで、登場するのが知識社会学なのである。
思想史/理念史との相違
思想史/理念史に関する先行研究ではボランティアを類型に分けるといったようにボランティアの実体的な理念と言説が対応しているという関係を前提とした研究であり、「本質」をめぐる議論は「よき価値・規範」を研究によって規定していく社会福祉学、教育学、応用倫理学といったものともこの書における「ボランティア的なものの語り」をメタ的に分析するというスタンスは異なるとまとめる。
言説分析との相違
そのスタンスによって社会学的な言説分析と呼ばれる方法論に近づくが、ミシェル・フーコーが編み出した「言説(ディスクール)分析」は語られたことの最小単位である「言表(エノンセ)」が形成=編成される規則性にしたがって「全体性」に迫るものであり、動員モデルの検討をするというこの書が持つ「社会/言説」という二重体の前提とは折り合いがつかない。本質主義や言説/実態という一意的な対応関係を排するという点では言説分析と共通するが、単純な関係を持たないからといって実質的な違いがあるとまで言い切るわけではないという。さらに、この書ではインタビューデータといった複数の質が異なる資料や行為を扱うことからも、「単位の確定性」という問題をはらみ、個々の発話から母集団を推定し全体性を捉えようとする、文字資料を対象とする言説分析とも距離を取らざるをえない。
構築主義との相違
また、社会問題を「状態」ではなく「クレイムメイキング」によって定義しようとする構築主義とも共通する視座を持つ。「当事者のクレイムとは独立した「実際の状態」の想定・言及を禁欲する強度」によって厳格派とコンテクスト派に分かれるのが構築主義であるが、<贈与のパラドックス>という特定の意味論形式を言説を整序する基準として分析枠組みに設ける方法は、構築主義とも相容れないという。
(弱い)知識社会学
「ボランティア的なもの」と「動員モデル」に迫るという問題設定に対し、否定的に方法論を整理する中で行き着いたのが知識社会学だという。通常、知識社会学は「◯◯ではなく~」という否定という形で中で言及されることが多い。もともと知識社会学の創始者であるマンハイムは、素朴にマルクス主義のみが真理とするイデオロギー論を批判するためにマルクス主義すらもイデオロギーとして適用し、また自らもイデオロギーに含めて、没価値的にさまざまな知識/事象を比較的に見て取る中で相関的に全体性を把握しようとするものであったとまとめる。
(知識社会学ですら)知識として存在(階級、世代、職業集団、学派 etc.)に拘束されてしまうことを「存在拘束性」とするのがマンハイムの創始した知識社会学のキーワードとし、さらに知識社会学の二要件をあげる。
- 知識(言説)/社会の二重体の実在を前提とする。
- 知識(言説)が社会に影響を与えるという因果関係を策定・重視する。
この書では①の要件については「動員モデル」を検証するという問題設定上は受け入れるのだが、同時に②の要件については社会と知識(言説)の対応関係を取らずに<贈与のパラドックス>を知識(言説)固有の意味論形式として相対化するため、完全に受け入れるものとできるわけではない。そのため、②の要件にある知識(言説)と社会との影響関係を視野に入れるがそれを相対化しつつも延命させるという微妙な距離感を持つ、という意味では「“弱い”知識社会学」の枠内であると方法論を策定している。
この弱い知識社会学における方法論では、仮説検証型というよりも、質的なさまざまなデータを調査・分析しながら理論/仮説生成をしていくタイプの方法論ということになる。得てきたデータが必ずしも代表性を持つわけではないが、それらデータと向き合う中で仮説を立ち上げ、否定的事例の発見によって立てられた仮説は棄却されるか、もしくは修正するというサイクルを「理論的飽和」に達するまで続けるという姿勢を持ち、そしてその検証するサイクルに厳密な終わりはない。
知識社会学とボランティア的なものの<贈与のパラドックス>と修正・同定関係
この書ではマンハイムだけでなく、ルーマンが自身の経験的研究を社会の意味論の分析に「知識社会学」と名付けたもので示されるコードとプログラムの区別などから影響を受けているという。「ボランティア的なもの」に解釈される<贈与のパラドックス>は「<贈与>なのか/<贈与>ではないのか」が確定されずに、「ボランティア的なもの」にどうしてもまつわる課題として浮き上がるが、それらをめぐる議論といったコミュニケーションを通じて絶えず「ボランティア」を同定しようとする。その同定の基準は話者の価値観や立場、時代的な背景といった条件によって異なるものの、展開していく過程は知識社会学という方法論において追うことが可能であり、また「動員モデル」という参加型市民社会の問題系と交差する中で捉えることができるというわけである。
おわりに
以上が、『「ボランティア」の誕生と終焉 <贈与のパラドックス>の知識社会学』序章で提示される研究の目的、問題設定、方法論の位置づけである。もっと突き詰めれば込み入った議論があるが、あくまでも自分自身が「自己責任」にまつわるディスコース研究を言語人類学や談話分析の観点から考えてきたという点で、細かな社会学的な議論に踏み込んでまとめたわけではないし、この書で述べられていることの妥当性を判断する能力を筆者は持ち得ていない。
そもそも、筆者は哲学的な興味関心と自分自身の置かれた立場から自然と「自己責任」というディスコースにまつわる問題意識と、言語人類学や批判的談話研究といった方法論と接してきたこともあって、独学で学ぶ社会学的な問題設定や方法論に関してはかなり手探りの部分があった。けれど、断片的にも勉強を積み重ねる中で、特に「ボランティア」にまつわるこの書における(弱い)知識社会学を用いた方法論の整理と分析は「自己責任」を分析していくにあたっても非常に示唆に富むものばかりで、とにかく勉強になり、序章以降の分析も(速読的な読み方ではあるが…)とても興味深く、また面白みと同時に理論・方法論の整理のみならず、大量の資料収集と分析をしていく様にすごみを感じた。
社会言語学といっても「社会“言語”学」といったように言語や相互行為に焦点が絞られたものが多く、日本ではほとんど(社会文化的な)ディスコース分析や言語人類学といった分野も浸透しておらず、また時代性を問いかけたフーコーによる「言説分析」的なものとしての批評性を伴ったものが希薄であるように感じている。その現状が一概に“悪い”とは思っていないし、本書で述べられているようにいかに自分自身の研究の目的・問題設定とに折り合いがつけられているかが研究においては重要で、社会批評的なものを「言えばそれでいい」とは微塵も思っていない。
しかし、筆者はやはりあくまでも研究の出発点として「自己責任」にまつわる「自由-行為-責任」にまつわるパラドキシカルな関係性や「自己責任」が表象される個々の文脈(自業自得、リスク管理、自主自立 etc.)と社会的問題や論点が捨象・切断されがちな現状への批判的意識があったことを、改めてこの書を読む中で思い起こしていった。
そういった意味でも、筆者にとって、この書で提起される問題意識や姿勢、研究成果には頭が上がらない。似た問題意識や関心を持つ方々に強くおすすめしたい一冊となった。
最後に、<贈与のパラドックス>という問題設定を仁平(2011)はどのように捉えているのか気になる方がいるかもしれない。一言でまとめると「<贈与のパラドックス>に対して向けられる第三者からのまなざしに怯むことなく、むしろその“偽善性”と向き合っていくことにより、異なる他者へと問いを分有し、討議していくことが<贈与>の意味論には含まれている」としている。<贈与のパラドックス>を批判的に検討していくのが本書の特徴であるが、最終的には「贈与的なものを肯定する地点」に至り、<交換>の輪を閉じないおくとして締めくくられるのである。
その意義について、社会文化コミュニケーションを研究する身としても三度噛みしめることとして、この記事を書いているが、前述したように僕はこの書を自信を持って理解できたとはとても言い難い。ぜひ、気になる方は実際に手にとって内容を確かめてみてほしい。
- 橋爪(2006)は「ここで、理論とは、具体的な研究に先立って組み立てられている、予測のことをいう。たとえば、物理学なら、研究に先立つ理論的予測があって、研究はそれを実証する。その予測(仮説)は、同時代の研究者の多くに共有されている。けれども、言説分析の場合、研究者は、言説みずからが語りだすことがらを、毎回「発見」するのである。(P195 )」と一般的な理論と言説分析を対比して説明している。 ↩︎