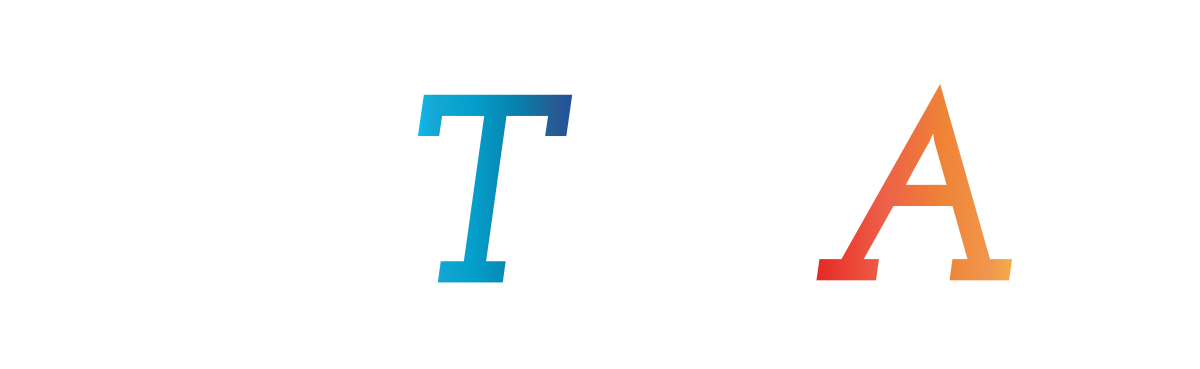ぼくが専門とする言語人類学、初対面会話などでどう説明するかいつも迷う。とりあえず、ことばと社会文化の関係を研究してるんですよ、というのがお決まりのフレーズだ。次にこぼす言葉も決まっている。要するにコミュニケーション論をやっています。あいまいで、ありきたりな心もとない紹介だと思う。しかし、現実に掲げる理想はデカい。なぜなら、「(あらゆる)ことばと社会文化の関係を研究している」、それがこの言語人類学的なコミュニケーション論だからだ。けれども、そんな途方もない野望を初対面会話で紹介することは叶わない。
この間、友人の結婚式に出た時だった。旧友との再会に緊張を覚えていた。というのも、かつての友人も、時が流れ、関係が変われば、態度も振る舞いも変わる。いつかの再会時に、どことなくヤンキー化を加速する旧友に僕はいくばくか怖気づく思いを抱いたのだった。結婚式当日、「レアキャラじゃん」「なにやってんの」と問われ、「研究してるよ」と答える。世間話をするうちに、旧友の姿はどこか落ち着いた様子に見えた。そんな僕の「どうしたの」「なんか大人になったね」という声かけに、「昔はあーんなだったけど」と笑いながら、腕と手を大きく宙に投げる旧友。
「そうそれ、その『あの』っていうのを研究してるのよ。『この・その・あの』の中で『あの』が一番遠いでしょ。『あの』に過去と今の自分の遠さが重なっていて、こういうことばに現れる無意識を見てるのよ」
「あっははは、確かに無意識だわ! でもそれしてどうすんのさ」
「意外に深いんだよちゃんと研究すると」
「まぁー深いんだろうけどね!」
これはかなり小気味よくコミュニケーション論を紹介できた例だった。きっと旧友にとって、自分の無意識の言葉づかいを意識した出来事になったことだろう。そうに違いない。
けれども、どうにも役立ちそうにないこともある。例えば、預かり知らぬ喜怒哀楽が爆発する瞬間。突発的な怒りは、その人が蓄積した感情を推進力にする。そうした誰かの怒りの琴線を、いつどこでどう踏み抜いてしまうかはわからない。怒りを誘発する出来事が、その因果的な由縁とも限らない。けれども、確かにほとばしる感情は伝播する。そして、その伝播が次なる感情を、振る舞いを、文化をつくっていく。
誰かにとっての偶然は、誰かにとっての必然でもある。けど、その交叉はコントロールできない。そこで、どんなに事後的に振り返ってみても、その場・その場で起きる出来事の偶然性を計り知ることはできない。
言語人類学をはじめとした社会文化的なコミュニケーション論は、旧友とのやりとりで挙げた具体的な文脈と場面を記録し、分析する。さらに、分析で得られた知見は研究者に共有され、『あの』といった文法形式のように、パターン化された記号として読み解かれていく。けれども、それは所詮、事後的な分析の産物であって偶然性そのものではない。事後から振り返れば必然的な出来事だけれども、むしろ一つ一つの出来事は偶然に開かれている。その固有性は、分析の過程でいつの間にか置き去りにされてしまうのだ。
そう考えると、どうにも役立ちそうにないのかもしれないコミュニケーション論は。