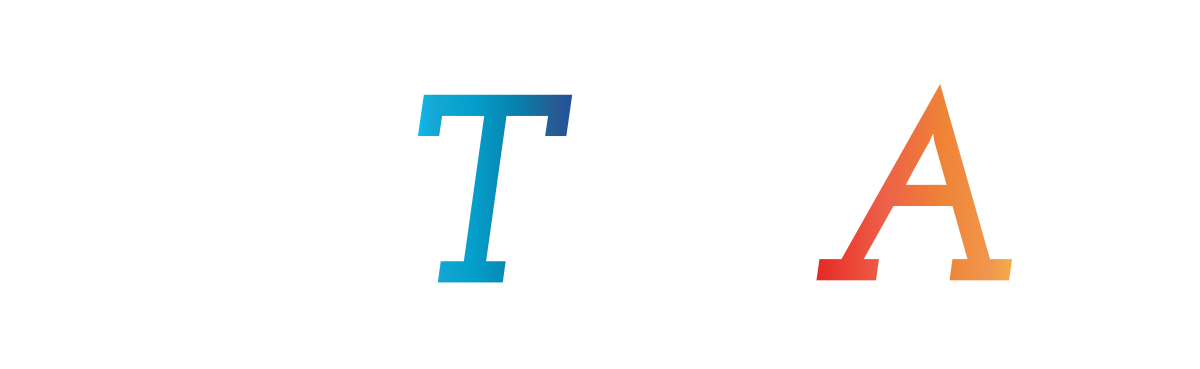論文概要
本論の目的は、アイデンティティ論を歴史化することである。より具体的には、冷戦構造時代の入口と出口という二つの時間においてアイデンティティ論がリベラリズムとの親和性を背景に形成されたことを指摘する。ホルクハイマーとアドルノの『啓蒙の弁証法』とタウシグの『ミメーシスと他者性』の読解を通して、本論の方法論となっている歴史化という手法を提示する。歴史化とは、理論が可能になる状況を含めて理論を検討することである。冷戦構造の出口にあたる時代、文化とアイデンティティは圧縮され同義語となり、それらが政治の構成要素となったといわれている。文化人類学において『文化を書く』は、文化とアイデンティティとの両方を流動性の考え方のもとに再構想した書物の一冊である。流動性は、多文化主義などに関する議論が高揚する中、リベラリズムと親和性をもっていた。文化、アイデンティティ、政治の交差点に形成されるこの問題系は、文化人類学にとっても疎遠なテーマではなかった。『菊と刀』は、日本という国を日本人の国にしているものが日本文化であることを前提にし、その内実を階層制と呼んだ。冷戦構造の出口にあたる時代、このような前提が批判されたことになる。しかし、アイデンティティの流動性はその固定化を前提にしたベネディクトへの批判としては有効である一方、両者ともリベラリズムと親和性を有している点では共通であり、状況との癒着を通して普遍性を確保している。この癒着が理論の持つ確信であり、それを打破するためには、誰にとってアイデンティティは流動的なのか、という問いを立てる必要がある。一例として、グアテマラ共和国のマヤ(系先住民)運動指導者を前にして、北米文化人類学者が抱くジレンマについて考察し、このジレンマは、アイデンティティが理論化される場所を歴史化できていないことに起因すると指摘する。
Ⅰ はじめに
Ⅱ 方法論―歴史化のために
Ⅲ 文化とアイデンティティとの同義語化―冷戦構造の出口で
Ⅳ アイデンティティ論の歴史化―冷戦構造の入り口で
Ⅴ マヤ運動における文化とアイデンティティ―北米人類学者のジレンマ
Ⅵ おわりに
“問題系”において機能するアイデンティティ論
「Ⅰ はじめに」で著者は自身の考えをこのように述べている。
アイデンティティと文化とがいまでも重要な概念として機能しているのは、自我同一性などをめぐる議論が継続している発達心理学ではなく、国家、権力、帰属、市民権などをめぐる問題系においてであり、その問題系は、哲学、政治学、歴史学、文化理論が交差する領域にある、と私は考えている。
Twitterでも言及したように、まさに”問題系”を主題として扱うCDS分野においてアイデンティティがテクストと幅広い社会文化的コンテクストと結びついて機能している点とかなり結びついてくるように思われる。
フレドリック・ジェイムソン(1989)が『政治的無意識』の冒頭で語った「つねに歴史化(historicize)せよ!」という一言を引きつつ、太田(2013)はこのように述べている。
ジェイムソンにとり、歴史化とはテクスト構造の客観的解明とは対局に位置し、解釈行為を力学として捉えることを意味した。すでに自然化してしまった読解を、どのような過程を通してその読解が自然化したのか、そのプロセスを問うのである。テクストの解釈行為のみならず、文化人類学における理論についても、同様の問いを立てることができるだろう。
おわりに
人類学の持つまなざしは個人的にとても好きだったのだが、あまりきちんと勉強してこなかったので改めてアイデンティティが人類学においてどのように語られているのかが気になっていた。
今回の論文はまさに文化人類学とCDSを接続する視点を与えてくれるもので、なかなか興味深く紹介した。
まだ全文は読めてもいないし、その他の文献でもどのように語られているのかまだまだ把握しきれていないが、これから少し目配せしていこうと思う。