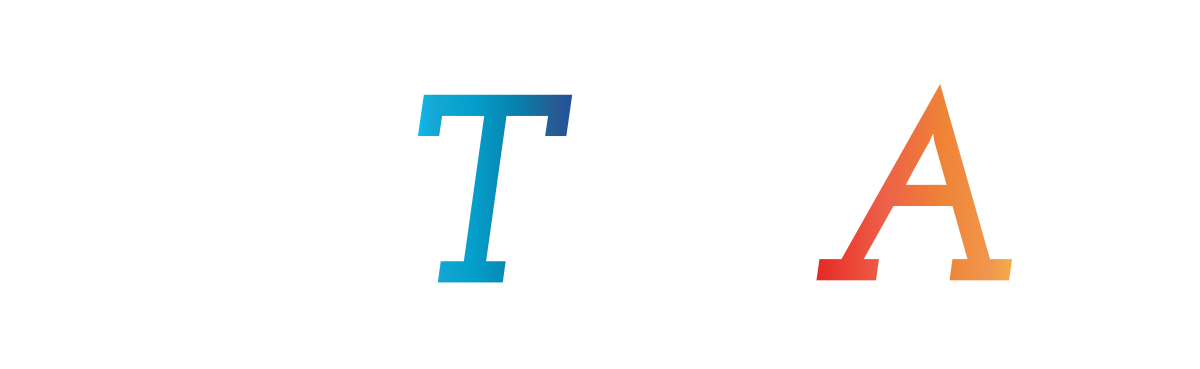前回の雑記「学問の自由は保身のための道具なのか」のつづき。ぼくは、人文社会科学系の研究者支援を考える学問バーのイベントに参加し、参加者が共通して前提としていると感じた「学問の自由」に違和感を覚えた。その違和感は、研究者の目線からばかり語っている点に尽きた。もちろん、研究者の陥っている状況や環境を考えるのだから研究者の目線からになるのはそれはそうだろう。けれど、研究者の地位を復権するためには弱い立場の研究者のことばかり考えるのは袋小路に思えた。そうではなく、必要なのは社会、いわば他者のことを考えることではないか。ぼくは100%そうだと思っている。
その上で、ぼくからいくつか問題提起をさしはさんだ。第一に、学術関係者に対する社会からの信頼を回復する必要がある。第二に、社会運動の知識経験は蓄積できたほうがいい。第三に、研究者と観客が交わることができ、まとまっているかのように見える雑談を考えたほうがいい。この問題提起は前回の雑記で挙げた問題意識と対応している。
そのなかでもぼくが実践できるし、その価値があると考えているのが雑談への洞察とその上での知恵を働かすことだ。理由は三つある。第一に、研究者の社会的立場の向上を訴えている人々は、結局のところその研究の価値をはかられることも考えることが大事だと思う。つまり、抽象的に学問・大学・研究の価値や立場を主張するのではなく、研究者がとるべき責任は新しい知的価値に対してのはずだ。これは、ぼくが「青山俊之」であるといった、研究者の「固有名」に関わる具体的で、他者との関係にも関わる。
第二に、そうして他者と関わるなかで蓄積されていくのが信頼関係であるからだ。知識経験を媒介にしようとも、研究者と観客の間で行なっているのは雑談だ。他者との関わりで必ずしも研究そのものを押し付けられないからこそ、それを媒介にしたコミュニケーションは不可避に思える。
第三に、雑談には人々が生きてきた歴史・社会文化的な身構え(スタンス)が投影される。その身構えは社会的につくられるものだから、研究者には研究者の、あえて大きくいうと「日本人」なら「日本人」の身構えが関わってくる。学術会議問題にあったように、ぼくは日本社会の公共性を考える上でこの歴史・社会文化的な規範に対する洞察が不可避に思えてならない。雑談に対する着目は、より根源的には社会・他者をよくするための知恵を磨き、その上での活動を積み重ねるのに有効だと考えた次第だ。
具体が大事といいながらも、雑談が大事、というぼんやりとした結論になってしまった。今後、試行錯誤しながら取り組んでいきたいと思っている。その過程で一点、重要だと思うのが雑談だからこそ雑談を意識しすぎないという点だ。雑談には可能性があるが、人と人をつなぐコミュニケーションに水を差してばかりいるのも野暮だろう。雑談の利点は変幻自在なそのキメラ性にある。その点を意識した知恵を働かしたほうがいいとぼくは思う。
雑談研究の導入は下記記事でもう少しまとめた。ひとまずこの辺で。ではでは。