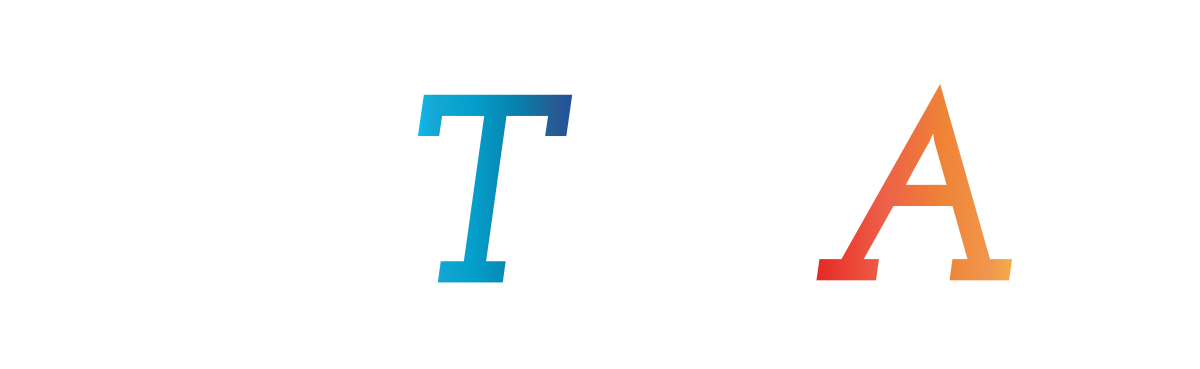「悪い時代の後には必ず良い時代が来る」
高浜寛によるマンガ『ニュクスの角灯』で登場するのがこのセリフだ。『ニュクスの角灯』は、明治前期の長崎を舞台に、西南戦争で親を亡くした主人公の美世、工芸品を輸入販売する道具屋の店主でフランス人のハーフである百年(通称モモ)を中心にしたアンティーク浪漫作品である。
主人公、美世がついた「嘘」
物語は、第二次世界大戦の最中、美世が空襲から避難する際、孫に自身の過去を回想することから始まる。回想では、皆苦を背負ったさまざまな人々との出会いを通じて成長する美世の生き様が描かれる。恋心とパリでの生活に一区切りがついたところで回想が終わり、戦火のなかで孫に語ったのが冒頭のセリフであった。その直後、長崎に原爆が落とされる暗い現実が描かれもするのだが、それだけではなく、きちんと未来への希望もほのかに示されて作品の幕は閉じられる。
美世のセリフ「悪い時代の後には必ず良い時代が来る」には、実は「原爆」という物理的な暴力だけではない、独特な陰影が宿っている。物語の冒頭、美世は人の手に渡っていた「物」から過去・未来を見通す神力のようなものを発揮していた。だが、途中でそれは見せかけのものであったことが発覚する。
美世が孫に語った最後のことばは、そんな見せかけの「おまじない」として孫にかけられたものでもあった。だが、作中では美世と孫が語り合った場面ではすでに亡くなった登場人物らが美世のその見せかけを孫にかけた「魔法」として肯定的に意味づける。虚実を織り交ぜた嘘の「嘘」が美世のセリフで、最後まで読み通した読者には胸に響くものがあった。
二度訪れた長崎
ぼくが『ニュクスの角灯』を読むきっかけとなったのは、昨年、長崎に訪れる機会ができたためだった。長崎には二度訪れたことがあったのだが、その経験もあってあの美世の「おまじない」が余計に染み入るところがあった。
はじめて長崎を訪れたのは学部生時代。1, 2日ほどの滞在に限られ、その時はろくに観光もできなかったのだが、印象に残っていたのはゲストハウスに貼られた反原爆ポスターの存在だった。広島のゲストハウスを訪れた時にも感じるところがあったのだが、「原爆」という負の経験・記憶はしっかりいまでもふとした街中に、人々の振る舞いに垣間見える。二度目に訪問できた際には、原爆資料館を訪れることを決めていた。
原爆資料館で考えた「たまたま」の理不尽さ

そして二度目の長崎観光で原爆資料館を訪れたのだが、資料館の展示は資料を読むよりも原爆の悲惨さをあたかも追体験するようアレンジされていることが、どうしても気に掛かった。いかに悲惨であったかを訴える展示は、過去を掘り下げるよりも、いまここに生きる観光客に過去の体験を強いる構造になっている。その構造は、現実の複雑さをどこか背景化してしまっているようにも思えてしまったからだ。
長崎が原爆のターゲットとなったのは実は「たまたま」だったことで知られている。もともとの投下予定は、北九州の小倉だった。原爆を投下する条件には、目視で確認できることがあったが、その日、つまり8月9日には視界不良のため、第三目標の長崎に原爆は投下された。
もちろん、実際に原爆が投下されたのは長崎であり、その現実は揺らぎようがない。ただ、「ありえたかもしれない」現実は実に入り組んだもので、理由にしにくい、「たまたまそうだった」という実際の出来事は、当事者としてはどうしても物語にしにくいという側面があるのだと思う。
「悪くない」おまじない
悲惨な戦争といえど過去の記憶となっていくなか、どうその複雑さを継承していくとよいのか。「悪い時代の後には必ず良い時代が来る」。これだけのことばを切り取れば実にありふれたものだろう。そもそも、フィクションで描かれたただの「おまじない」であって、現実に突然やってくるたまたまの理不尽さを消し去る効果があるわけでもない。だが、それが未来に生きる子どもに向けられたものだと思えば、『ニュクスの角灯』で描かれる時代とその中で翻弄される人間の明暗に触れたからこそ、このことばは確かに「悪くない」おまじないとして胸に響いた。
二度目の長崎滞在で考えたことについては、次のエッセイでも記しています。