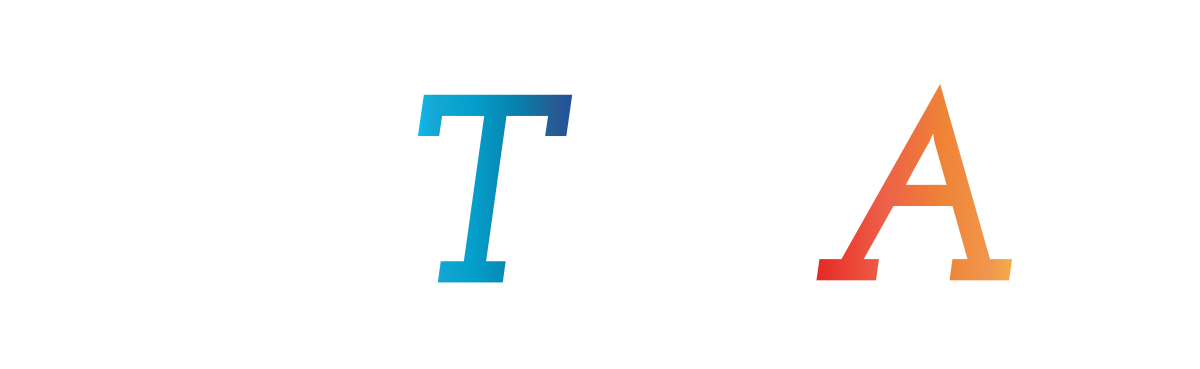研究論文を書いていると、たどり着きたい論点に向かってつい筆が滑ってしまう。言い換えると、その論点の意味が「わかる」ように、説明しすぎてしまう。長らくこの問題にぼんやり気づいていたけど、なかなか改善されにくいことだった。自分ではうまくまとめて書いているつもりだから少しタチが悪い。実際、要約が「うまい」と言われることもある。けど、問題の核がようやくわかった。どうやら「自分自身の理解過程」を文章に投影する傾向にあるらしい。
おそらく、ぼくは「過去の自分自身」を仮想的な読み手にしている。これは一種、新しいことを書くことへの「甘え」であり、同時に読み手への「無責任」な態度だと思った。特に研究や批評では、「新しい情報が増える」ことが重要である。議論をまとめても情報はあまり増えない。したがって、書くべきはぼくが見出した「新しさ」だ。また、議論をまとめることで自分の思考過程がたどれると思っている節がある。しかし、どんなに丁寧に尽くしたとしてもそれは嘘だろう。ぼくがせめて果たせるのは、読み手への納得感であって、思考の投影ではない。
また、自分が納得しにくい文章に納得がいかないことが多かった。その理解のために余計な時間を費やしたとさえときに思ってきた。だからこそ、せめて自分は納得できるように文章を書こうと努めた。しかし、それは一種の倒錯なのかもしれない。読み手には読み手の自由な読みがあり、また責任がある。
だからぼくがなすべき責任は、新しさへの思考を、文章を研ぎ澄ませることだろう。気づくのが遅かった。けど、こうした遠回りこそが自分の足場を確かめていくことでもあるのだと思う。そういうことにしておく。
言い訳をすると、どうしても自分の研究内容が多分野の議論をまたぐこと、言語人類学という研究分野が物語よりも記述に特化した学問であることと、この自分の傾向は合致しているのだと思う。これまではある意味で配慮しようとしすぎた。けど、もうそこまで変に配慮する必要もない立ち位置になってきた気がする。