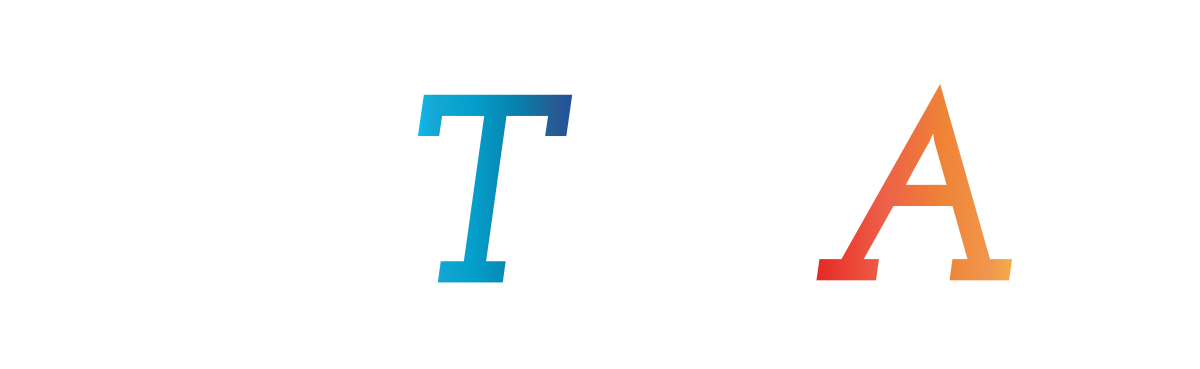「およそ語られうることは明晰に語られうる。そして、論じえないことについては、人は沈黙せねばならない。」
『論理哲学論考』(野矢茂樹訳、岩波文庫、p.9)
哲学者・ウィトゲンシュタイン(1889-1951)の著作『論理哲学論考』(1921年、以下『論考』)の冒頭のことばでは、本書の内容がこのように要約される。要するに、哲学が取り組んできた「真理」の考究が無意味だったことをウィトゲンシュタインは『論考』で示した。しばしばウィトゲンシュタインの初期著作『論考』が反哲学と言われる所以だ。けれども、ウィトゲンシュタインはのちに自身のこの結論をなかば撤回する著作として『哲学探究』を執筆する。ウィトゲンシュタインのこの潔さに、気難しくも、誠実な姿勢にぼくは好感を抱いてきた。「語りえぬものについては、沈黙せねばならない」、厨二病的ともいえるが、語り手の気骨さが浮かび上がる、シビれることばだ。
とはいえ、ウィトゲンシュタインの『論考』はその厳密な論理展開に読み通すことができないままでいた。ウィトゲンシュタインの解説本のなかで、訳者が同じという理由でずいぶん昔に買っていたのが野矢茂樹さんの『ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む』(2006年 [2002年]、以下『論考を読む』)だった。何の気なしに『論考を読む』の最後だけ読んだところ、思うことがあったので簡単に書き残す。
野矢茂樹さんの『論考を読む』は基本的に『論考』の文言を引きながら解説する書籍だ。けれども、最後に、野矢さんは『論考』に抗い、「『論考』の向こう」という章を書いている。ウィトゲンシュタインに負けじとした野矢さんの気骨さを感じた。単純に哲学書を読まない、哲学的な態度に好感を覚える。とはいえ、野矢さんの主張をざっくり述べると、『哲学探究』から『論考』を読み直し、『論考』でウィトゲンシュタインが結論づけたような言語・論理に閉じることはない、というのだ。つまり、論理的言語からこぼれ出る他者との出会いに開かれているという。
細かいことはここでは書かないけれども、『哲学探究』から『論考』を読み直そうとも、そこで展開されている他者と出会う議論は、基本的にウィトゲンシュタインと同様に、特定の言語に閉じている。というのも、論理学的な思考で「真偽」に還元されたり、あるいは真偽命題からはみ出すパラドックスとその言語ゲーム(子どもの遊びに見られるような不定形なルール)に還元したりしており、言ってしまえば象徴的な次元からコミュニケーションの次元を神秘化しているように思えた。このパターンは哲学的な議論にしばしば見られる。
ここでいう、コミュニケーションの次元は、アメリカの数学者・哲学者のC.S. パースの記号論でいえば指標性と呼ばれるものだ。指標性というのは、風見鶏が方角を指すように、連続的な記号の関係を指す。キャンプ時に煙が上がっているのを見ると焚き火があることを思い浮かべ、街中のビルから立ち上る煙を見ると火事を思い浮かべる、こういった関係が指標性だ。これら例にもあるように、生活で習慣的に感知する文脈・推測が指標性の意味づけに関連する。そのように考えると、指標性の次元、つまり日常的に出会う記号的なコミュニケーションの次元はかなり広い。さらに言うと、象徴性・指標性・類像性は組み合わさってわたしたちの言語・コミュニケーションを彩る。だから、象徴性、つまり論理的言語に限界があるから、そこからはみ出す他者・身体・自然を安易に神秘化するのはウィトゲンシュタインの過ちを繰り返してしまっているようにぼくには見えてしまうのだ。
ところで、『論考を読む』を締めくくることばが次のものだ。
語りきれぬものは、語り続けねばならない。
『論考を読む』(2006年 [2002年]、p.323)
このことばを初めて見たとき、ことばの響きだけでシビレたのを覚えている。確かぼくが大学2年生のときだった。当時、ウィトゲンシュタインの哲学を題材にして、ゼミに参加する志望動機書を書いたのを今でも覚えている。今一度、なにをどう「語り続けねばならない」のか、自分のことばで考えていきたい。